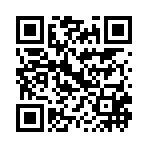2014年01月26日
「ウガンダすごろく」
番町市民活動センターでのランチトーク。

おもしろいワークショップのミニ
体験がありました。
「ウガンダすごろく」!
今回のランチトークゲストは、JICA青年海外協力隊員として
2年間ウガンダで活動された大塚泰法さん。
 ウガンダでは、セント・ムバガ中等学校で子どもたちにパソコン指導やバレー部の部活指導など、教育活動をされたそうです。
ウガンダでは、セント・ムバガ中等学校で子どもたちにパソコン指導やバレー部の部活指導など、教育活動をされたそうです。
その大塚さんが作ったのが、ウガンダの子どもたちの現状を人生ゲームのようなすごろくで疑似体験する「ウガンダすごろく」
ランチトーク参加者もちょっと体験させていただきました。
都会に暮らす裕福な子どもと、貧しい農村部で暮らす子どもとでは、教育や日常生活でどのくらい格差が生まれるのか、ウガンダではどんなことが、子どもたちが教育を受ける妨げとなっているのか、ゲームをしながら理解することができました。
ウガンダは高等学校まで授業料が無償化されているとのこと。また、子どもたちの多くが寮生活をしているそうです。授業料が無償化されても、寮費や食費、教材費などのお金が払えず、卒業できない子どもたちもいるそうです。半面、都市部に住む裕福な家庭の子どもは有料の私立学校に通い、携帯やパソコンを持ち、恵まれた暮らしを送っているそうです。この格差はますます広がっているとのこと。
ゲームをしながら、ウガンダという国の一面を学ぶことができました。
開発教育ではこのような教材を使い、ワークショップが行われます。子どもから大人まで、世代を越えての国際理解にはゲームやアクティビティは欠かせません。
なかなか面白いこのアクティビティ、いつかワクらぼで企画できたらいいなと思っています!

おもしろいワークショップのミニ
体験がありました。
「ウガンダすごろく」!
今回のランチトークゲストは、JICA青年海外協力隊員として
2年間ウガンダで活動された大塚泰法さん。
 ウガンダでは、セント・ムバガ中等学校で子どもたちにパソコン指導やバレー部の部活指導など、教育活動をされたそうです。
ウガンダでは、セント・ムバガ中等学校で子どもたちにパソコン指導やバレー部の部活指導など、教育活動をされたそうです。その大塚さんが作ったのが、ウガンダの子どもたちの現状を人生ゲームのようなすごろくで疑似体験する「ウガンダすごろく」
ランチトーク参加者もちょっと体験させていただきました。
都会に暮らす裕福な子どもと、貧しい農村部で暮らす子どもとでは、教育や日常生活でどのくらい格差が生まれるのか、ウガンダではどんなことが、子どもたちが教育を受ける妨げとなっているのか、ゲームをしながら理解することができました。
ウガンダは高等学校まで授業料が無償化されているとのこと。また、子どもたちの多くが寮生活をしているそうです。授業料が無償化されても、寮費や食費、教材費などのお金が払えず、卒業できない子どもたちもいるそうです。半面、都市部に住む裕福な家庭の子どもは有料の私立学校に通い、携帯やパソコンを持ち、恵まれた暮らしを送っているそうです。この格差はますます広がっているとのこと。
ゲームをしながら、ウガンダという国の一面を学ぶことができました。
開発教育ではこのような教材を使い、ワークショップが行われます。子どもから大人まで、世代を越えての国際理解にはゲームやアクティビティは欠かせません。
なかなか面白いこのアクティビティ、いつかワクらぼで企画できたらいいなと思っています!

2013年10月14日
国際ガールズ・デー
10月11日は「国際ガールズ・デー」
世界の国々、とりわけ開発途上国では女子(18才未満)の多くが経済的、文化的な理由により学校に通えず、10代前半での結婚を余儀なくされ、貧困の中で暮らしています。また先進国においても、女子には様々な社会的制約が存在します。しかし、適切な教育と支援を受けることができれば、彼女たちの可能性は無限に広がり、未来は大きく変えられるのです。こうしたことから、国際社会は女子の持つ可能性に注目し、2011年12月、国連総会において10月11日を「国際ガールズ・デー(International Day of the Girl Child)」と定めました。(~国際連合広報センターHPより~)
 世界中でいろいろなイベントが開催されました。
世界中でいろいろなイベントが開催されました。
日本でも、国連大学で「世界を変えるもう一人のマララたち」という記念イベントが開催されました。
その様子はプラン・ジャパンのHPに詳しく報告されています。ぜひご覧ください。
http://www.plan-japan.org/girl/news/131010.html
国連本部でのマララさんのスピーチは上記国連広報のHPより日本語字幕付きで見ることができます。彼女の凛として希望に満ちた呼びかけをぜひお聴きください
http://www.unic.or.jp/
世界の国々、とりわけ開発途上国では女子(18才未満)の多くが経済的、文化的な理由により学校に通えず、10代前半での結婚を余儀なくされ、貧困の中で暮らしています。また先進国においても、女子には様々な社会的制約が存在します。しかし、適切な教育と支援を受けることができれば、彼女たちの可能性は無限に広がり、未来は大きく変えられるのです。こうしたことから、国際社会は女子の持つ可能性に注目し、2011年12月、国連総会において10月11日を「国際ガールズ・デー(International Day of the Girl Child)」と定めました。(~国際連合広報センターHPより~)
 世界中でいろいろなイベントが開催されました。
世界中でいろいろなイベントが開催されました。日本でも、国連大学で「世界を変えるもう一人のマララたち」という記念イベントが開催されました。
その様子はプラン・ジャパンのHPに詳しく報告されています。ぜひご覧ください。
http://www.plan-japan.org/girl/news/131010.html
国連本部でのマララさんのスピーチは上記国連広報のHPより日本語字幕付きで見ることができます。彼女の凛として希望に満ちた呼びかけをぜひお聴きください

http://www.unic.or.jp/
2013年09月25日
絵本を届ける
 静岡市美術館で『絵本原画の世界』と題して、懐かしいそして今でも愛されている絵本の原画展が開催されています。
静岡市美術館で『絵本原画の世界』と題して、懐かしいそして今でも愛されている絵本の原画展が開催されています。子ども連れの若いお父さん・お母さんがたくさん来ていました。
 会場で絵本を読めるコーナーもあり、子どもたちは(むかし子どもだった大人たちも)楽しげに絵本の世界を満喫しているようでした。
会場で絵本を読めるコーナーもあり、子どもたちは(むかし子どもだった大人たちも)楽しげに絵本の世界を満喫しているようでした。子どもたちにとって、絵本は最初に触れる文学です。文字と絵からなる物語は、想像力の源であり、希望でもあります。
それは、どこの国でも変わりありません。
公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会では「絵本を届ける運動」を続けています。
カンボジア、ラオス、ミャンマー難民キャンプ、アフガニスタンなどに絵本を届けています。日本の絵本の日本語の文章に、それぞれの国の文字の翻訳シールを貼って、その国の子どもたちが文字を学び、絵本を楽しめるように、そんな工夫をしての運動です。
とっても素敵な取り組みだと思っています。
http://sva.or.jp/activity/program/ehon/outline.html
絵本と翻訳シールをセットで購入し、シールを貼った絵本を作り、それをシャンティに預ける、という形で子どもたちに届けてもらいます。
シールを貼るのはボランティアでも、絵本セットは購入しなければなりません。
ワクらぼでもこの取り組みに参加したいと思っています。
どんな形で企画できるでしょうか? お金のかかるボランティアに皆さんが参加してくださるでしょうか?…
絵本を読むことで、子どもたちの笑顔が世界中に拡がっていくことを願って、いつか企画をお届けしますね

2013年09月19日
読書の秋にお薦め1冊
『旅に出よう 世界にはいろんな生き方があふれてる』
 近藤雄生 著 岩波ジュニア新書(2010年)
近藤雄生 著 岩波ジュニア新書(2010年)
世界を旅した紀行文はたくさんありますが、この本は開発教育という視点からとらえても大変興味深く面白い本だと思います。
岩波ジュニア新書は、中学校や高校に通う若い世代を対象に書かれていますが、一般の人でも十分に楽しめます。
20代、社会に出たばかりの近藤さんが、奥様とともに、オーストラリアを起点として、東南アジア、中国、中央アジアの国々を経て、ヨーロッパ、アフリカを回り、日本に帰国するまでの5年間の旅の中で、目にしたこと・体験したこと、そして感じたことのほんの一部(だと思います)を紹介してくれています。
この本に書かれていることは、開発教育の分野で伝えたいと思っている、そんな世界の現状そのものなのです。
ビルマからタイへ難民として逃れ、そこで学んでいる若者たち。彼らの多くは「学ぶ」ことの素晴らしさを感じ、いつか母国のために活躍したいと願っています。
情勢不安のチベットから亡命した人たちが一番たくさん暮らしているのは、ヨーロッパではスイスだということも初めて知りました。
近藤さんは、旅先でその国の言葉を学び、その地で暮らす人たちに直接会って、彼らの想いを聞く、ということから始めています。
彼らとの触れ合いが、「世界にはいろんな生き方があふれてる」という副題になったのでしょう。自分とは違う生き方、異なる価値観をどう受け止めるか、という問題の一つの答えだと思うのです。そしてそれを、若い世代に伝えたいと思っているのだと感じます。
優しい語り口で気軽に読むことのできる一冊です。読書の秋に、ぜひ!
 近藤雄生 著 岩波ジュニア新書(2010年)
近藤雄生 著 岩波ジュニア新書(2010年)世界を旅した紀行文はたくさんありますが、この本は開発教育という視点からとらえても大変興味深く面白い本だと思います。
岩波ジュニア新書は、中学校や高校に通う若い世代を対象に書かれていますが、一般の人でも十分に楽しめます。
20代、社会に出たばかりの近藤さんが、奥様とともに、オーストラリアを起点として、東南アジア、中国、中央アジアの国々を経て、ヨーロッパ、アフリカを回り、日本に帰国するまでの5年間の旅の中で、目にしたこと・体験したこと、そして感じたことのほんの一部(だと思います)を紹介してくれています。
この本に書かれていることは、開発教育の分野で伝えたいと思っている、そんな世界の現状そのものなのです。
ビルマからタイへ難民として逃れ、そこで学んでいる若者たち。彼らの多くは「学ぶ」ことの素晴らしさを感じ、いつか母国のために活躍したいと願っています。
情勢不安のチベットから亡命した人たちが一番たくさん暮らしているのは、ヨーロッパではスイスだということも初めて知りました。
近藤さんは、旅先でその国の言葉を学び、その地で暮らす人たちに直接会って、彼らの想いを聞く、ということから始めています。
彼らとの触れ合いが、「世界にはいろんな生き方があふれてる」という副題になったのでしょう。自分とは違う生き方、異なる価値観をどう受け止めるか、という問題の一つの答えだと思うのです。そしてそれを、若い世代に伝えたいと思っているのだと感じます。
優しい語り口で気軽に読むことのできる一冊です。読書の秋に、ぜひ!

2013年08月20日
ミレニアム開発目標
 ミレニアム開発目標=MDGs(Millennium Development Goals)
ミレニアム開発目標=MDGs(Millennium Development Goals) 世界から貧困をなくすために、世界(国連)が2000年に作った開発目標です。
8つのゴールを定め、2015年をそのゴールの年と定めています。
2000年までを基準にして、世界の貧困を半分に減らそう、という目標です。
その目標を達成するために、ユニセフをはじめとする国連の機関や、各国政府、国際機関やNGOなどが協力して活動を進めています。
このミレニアム開発目標、日本ではあまり知られていないように思います。
国連が定めたものであり、本当に達成可能なのか疑問に思う方も多いのでは?
でも、目標はないよりもあったほうがよく、その目標に向かって助け合いながら活動することに、大きな意味があると思います。
草の根レベルの活動から、国を越えた大規模な支援まで、私たちにできることは様々です。できることは限られていても、その限られた範囲で自分たちにできることがあるのではないか? そう思いながらワクらぼは活動しています。
9月~10月にかけて、今年も STAND UP TAKE ACTIONキャンペーンの季節がやってきます。貧困解決のために、一歩を踏み出そうというキャンペーンです。
今年も一歩を踏み出すための、その一歩を皆さんと共有できたらうれしいです。
ミレニアム開発目標に興味のある方はこちらを
→ http://www.undp.or.jp/mdgsafrica/
STAND UP TAKE ACTIONのことを知りたい方はこちらを覗いてみてください

→ http://www.standup2015.jp/index.html
2013年07月14日
マララさん国連スピーチ
昨年10月武装勢力に襲撃され負傷したパキスタンの少女、
マララ・ユスフザイさんが、12日午前(現地時間)、ニューヨークの国連本部でスピーチを行いました。
彼女が訴え続けているのは「学ぶ権利」。それは、性別、国籍、所属する社会、貧富の差…などに関係なく、この世界に生まれたすべての子どもたちに与えられるべきものであると、力強く呼びかけています。
16歳の少女の、熱く、真直ぐな信念は、その堂々たるスピーチとともに、聴く者の心に深く沁みこみます。
私たちが何をすればよいのか、答えは簡単に見つかりません。でも、深く思うこと、そして一歩前に踏み出すことがいかに大切かを、彼女は私たちに示してくれている気がします。
彼女の英語でのスピーチと、その日本語訳は以下のHPからご覧いただけます。
ぜひ、生の声、その思いをお聴きください
http://www.huffingtonpost.jp/2013/07/12/malala_speech_n_3588163.html
マララ・ユスフザイさんが、12日午前(現地時間)、ニューヨークの国連本部でスピーチを行いました。
彼女が訴え続けているのは「学ぶ権利」。それは、性別、国籍、所属する社会、貧富の差…などに関係なく、この世界に生まれたすべての子どもたちに与えられるべきものであると、力強く呼びかけています。
16歳の少女の、熱く、真直ぐな信念は、その堂々たるスピーチとともに、聴く者の心に深く沁みこみます。
私たちが何をすればよいのか、答えは簡単に見つかりません。でも、深く思うこと、そして一歩前に踏み出すことがいかに大切かを、彼女は私たちに示してくれている気がします。
彼女の英語でのスピーチと、その日本語訳は以下のHPからご覧いただけます。
ぜひ、生の声、その思いをお聴きください

http://www.huffingtonpost.jp/2013/07/12/malala_speech_n_3588163.html
2013年06月25日
ユニセフ「国際協力講座」
国際協力と言ってもその関わり方は様々です。
まず、私たちが思い浮かべるのは、開発途上国でその国の人々とともによりよい明日を築くための活動。JICAや民間のNGOなどが、教育・生活・医療など様々な分野で取り組みを続けています。厳しい環境で頑張っている人たちがたくさんいます。
そんな人たちの生の声を聴き、世界の現状を知ることは大切な国際協力の1つだと思います。開発教育では、ゲームやワークショップを活用して現状をお伝えする場を作っています。JICAやNGOでは、報告会や学習会を開催し情報提供をしています。
一方、現地に行かず、日本国内で支援活動を続けている団体もたくさんあります。衣類をはじめ生活必需品を直接現地に届ける活動、現地に病院や学校を建てるための資金を集める活動。物的支援だけでなく、優秀な人材を派遣する人的支援のために活動している団体もあります。
このような国際協力活動を行う上で、やはり基礎的な知識は必要です。メディアやインターネットの発達で、情報を手にする機会は格段に増しました。だからこそ、しっかりした知識を身につけ、その理解のもと活動に取り組む事は大切なことだと考えます。関わり方が様々であるということは、学ぶべき知識も多様だということです。どの分野から学ぶのか…当然ながら自分の興味のある分野から学ぶのがよいのでは!
そこから底辺を広げ、横へ縦へと関心を拡げていくと、その分野分野で視点が変わり、気づきも増します。自分の世界が広がるとともに、新しい出会いも生まれるのではないでしょうか?
ユニセフが今年も「国際協力講座」を開催します。
東京・品川のユニセフハウスで10月からおよそ半年。英語での講義もあり、受講資格はなかなか厳しいです。興味のある方はぜひチャレンジしてください。
どんな講義があるのか、どんな方が講師を務めるのか、HPをのぞいてみるだけでもおもしろいですよ。
http://www.unicef.or.jp/inter/inter_kouza.html
まず、私たちが思い浮かべるのは、開発途上国でその国の人々とともによりよい明日を築くための活動。JICAや民間のNGOなどが、教育・生活・医療など様々な分野で取り組みを続けています。厳しい環境で頑張っている人たちがたくさんいます。
そんな人たちの生の声を聴き、世界の現状を知ることは大切な国際協力の1つだと思います。開発教育では、ゲームやワークショップを活用して現状をお伝えする場を作っています。JICAやNGOでは、報告会や学習会を開催し情報提供をしています。
一方、現地に行かず、日本国内で支援活動を続けている団体もたくさんあります。衣類をはじめ生活必需品を直接現地に届ける活動、現地に病院や学校を建てるための資金を集める活動。物的支援だけでなく、優秀な人材を派遣する人的支援のために活動している団体もあります。
このような国際協力活動を行う上で、やはり基礎的な知識は必要です。メディアやインターネットの発達で、情報を手にする機会は格段に増しました。だからこそ、しっかりした知識を身につけ、その理解のもと活動に取り組む事は大切なことだと考えます。関わり方が様々であるということは、学ぶべき知識も多様だということです。どの分野から学ぶのか…当然ながら自分の興味のある分野から学ぶのがよいのでは!
そこから底辺を広げ、横へ縦へと関心を拡げていくと、その分野分野で視点が変わり、気づきも増します。自分の世界が広がるとともに、新しい出会いも生まれるのではないでしょうか?
ユニセフが今年も「国際協力講座」を開催します。
東京・品川のユニセフハウスで10月からおよそ半年。英語での講義もあり、受講資格はなかなか厳しいです。興味のある方はぜひチャレンジしてください。
どんな講義があるのか、どんな方が講師を務めるのか、HPをのぞいてみるだけでもおもしろいですよ。
http://www.unicef.or.jp/inter/inter_kouza.html
2013年06月03日
上映会参加後記『モンサントの不自然な食べ物』
『モンサントの不自然な食べ物』というドキュメンタリー映画を観ました。
上映してくれたのは、富士山麓有機農業推進協議会(http://fujisan-yuuki.com/)。
モンサントはアメリカに本社を置くバイオ化学の多国籍企業。世界の遺伝子組み換え市場の90%を占めるグローバル企業です。これは、その巨大企業の裏側を、多くの人の証言や文書から丁寧に追いかけた長編ドキュメンタリーです。
監督はフランス人女性、マリー=モニク・ロバン。2008年製作。
詳しくはこちらをご覧ください→http://www.uplink.co.jp/movie/2012/711
このドキュメンタリーは私たちに多くを問いかけます。多国籍企業の実態、遺伝子組み換えの現状、食の安全性、農業の未来… 重いテーマの作品です。考えさせられることは多く、しかもすぐに答えの出るものではありません。また一人ひとりの個人の力ではどうにもならない現実がそこにはあります。
食の問題には、富める国・経済的に貧しい国の格差が如実に表れます。農業を暮らしの糧としている経済的に貧しい国の人々にとって、収穫量の増減は直接自分たちの生活に結びつく切実な問題です。富める国の巨大な権力はそんな彼らの足元を見て、自分たちの利益追求の手を休めません。このようなことは世界のいたるところで起こっているはずです。そして富める国はますますその力を強め、経済的に貧しい国はその状況からなかなか抜け出すことができないのです。
私たちはそれらの事実を知らなければなりません。まず「知る」ことから始めましょう。
受け取り方や考え方は人によって様々でしょう。でも知ることによって、私たちは「同じ問題やテーマを考えるという時間」を共有できると思うのです。感じ、考える時間を共有すること(感じ、考えることがおのおの違っても)は現代を生きる私たちにとって、とても大切なことだと考えます。
『モンサントの不自然な食べ物』はそんなことを考えさせてくれる映画となりました。
食をテーマにしたドキュメンタリー映画『よみがえりのレシピ』が、6月下旬から静岡市のシネ・ギャラリーでロードショーされます。こちらは在来作物を守る人々の物語です。
ワクらぼでもご紹介させていただきました。
たくさんの方に観ていただきたいと思います。お時間のある方、ぜひお出かけください!
上映してくれたのは、富士山麓有機農業推進協議会(http://fujisan-yuuki.com/)。
モンサントはアメリカに本社を置くバイオ化学の多国籍企業。世界の遺伝子組み換え市場の90%を占めるグローバル企業です。これは、その巨大企業の裏側を、多くの人の証言や文書から丁寧に追いかけた長編ドキュメンタリーです。
監督はフランス人女性、マリー=モニク・ロバン。2008年製作。
詳しくはこちらをご覧ください→http://www.uplink.co.jp/movie/2012/711
このドキュメンタリーは私たちに多くを問いかけます。多国籍企業の実態、遺伝子組み換えの現状、食の安全性、農業の未来… 重いテーマの作品です。考えさせられることは多く、しかもすぐに答えの出るものではありません。また一人ひとりの個人の力ではどうにもならない現実がそこにはあります。
食の問題には、富める国・経済的に貧しい国の格差が如実に表れます。農業を暮らしの糧としている経済的に貧しい国の人々にとって、収穫量の増減は直接自分たちの生活に結びつく切実な問題です。富める国の巨大な権力はそんな彼らの足元を見て、自分たちの利益追求の手を休めません。このようなことは世界のいたるところで起こっているはずです。そして富める国はますますその力を強め、経済的に貧しい国はその状況からなかなか抜け出すことができないのです。
私たちはそれらの事実を知らなければなりません。まず「知る」ことから始めましょう。
受け取り方や考え方は人によって様々でしょう。でも知ることによって、私たちは「同じ問題やテーマを考えるという時間」を共有できると思うのです。感じ、考える時間を共有すること(感じ、考えることがおのおの違っても)は現代を生きる私たちにとって、とても大切なことだと考えます。
『モンサントの不自然な食べ物』はそんなことを考えさせてくれる映画となりました。
食をテーマにしたドキュメンタリー映画『よみがえりのレシピ』が、6月下旬から静岡市のシネ・ギャラリーでロードショーされます。こちらは在来作物を守る人々の物語です。
ワクらぼでもご紹介させていただきました。
たくさんの方に観ていただきたいと思います。お時間のある方、ぜひお出かけください!

2013年05月13日
シリア危機
静岡新聞、日曜日の社説をお読みになった方も多いことでしょう。
社説はこう始まります。
「もうたくさん。もうたくさん。2年以上も続く内戦で7万人を超える死者を出し、その中には何千人もの罪のない子どもたちが含まれ…」。国連のビデオメッセージはこんな悲痛な言葉で始まる。・・・・・ (静岡新聞 2013年5月12日(日)朝刊より)
シリアの危機は私たちの想像をはるかに超えています。たくさんの人が傷つき、家を追われ、子どもたちから笑顔が消えました。
国連リーダーたちの訴えは深刻です。
そのメッセージをこちらからみていただくことができます。
http://www.japanforunhcr.org/activities/theme_em-syria/
彼らは、私たち個人だけでなく、国及び各国のリーダーたちにも厳しく訴えます。
本当に切実なメッセージだと思います。
こういう現状を知ること、それを多くの人に伝えること、そして何よりも自分自身が声をあげていくことを開発教育は目指します。
できることは人それぞれです。でも必ずできることがある、と信じて!
社説はこう始まります。
「もうたくさん。もうたくさん。2年以上も続く内戦で7万人を超える死者を出し、その中には何千人もの罪のない子どもたちが含まれ…」。国連のビデオメッセージはこんな悲痛な言葉で始まる。・・・・・ (静岡新聞 2013年5月12日(日)朝刊より)
シリアの危機は私たちの想像をはるかに超えています。たくさんの人が傷つき、家を追われ、子どもたちから笑顔が消えました。
国連リーダーたちの訴えは深刻です。
そのメッセージをこちらからみていただくことができます。
http://www.japanforunhcr.org/activities/theme_em-syria/
彼らは、私たち個人だけでなく、国及び各国のリーダーたちにも厳しく訴えます。
本当に切実なメッセージだと思います。
こういう現状を知ること、それを多くの人に伝えること、そして何よりも自分自身が声をあげていくことを開発教育は目指します。
できることは人それぞれです。でも必ずできることがある、と信じて!

2013年03月31日
開発教育を考える⑰~フェアトレード~
 タイシルクのスカーフ。
タイシルクのスカーフ。日本でフェアトレードを扱っている「第3世界ショップ」の品物です。
フェアトレードショップテーボムさんで見つけました。
このスカーフは繭玉の一番外側の部分を使って作っているそうです。手織りで作られています。コットンのようなガーゼのような、春のふんわりとした雰囲気が伝わります。
 フェアトレードというとなんだか値段が高くてデザインが今一つ、作りも悪い…なんて思っていませんか?そんなことはありませんよ。
フェアトレードというとなんだか値段が高くてデザインが今一つ、作りも悪い…なんて思っていませんか?そんなことはありませんよ。手織りですから、網目の大きさがそろっていないところがあります。蚕の繭の一番外側の荒いところを使っていますから、シルクのすべすべした感じはありませんが、素朴でやさしい製品に仕上がっています。市場に出され購買されるものですから、品質もしっかりしています。しかもお値段が手頃です。
フェアトレードという概念が日本ではなかなか理解されないのが残念です。フェアトレードはボランティアではありません。きちんとした経済モデルとして世界の中で地位を得ています。作り手から買い手へ適正な価格でものが売り買いされること、そして作り手が不利益を被らないようにその商品に対する正しい対価が支払われていること、対価が支払われることによって、作り手(主に途上国の人々)の生活が向上し、子どもを学校に通わせ、生活するために必要な設備(水道やトイレ、病院や学校など)を整備できるようになること、などをめざしてフェアトレードという経済活動は生まれたのです。
フェアトレードの商品は作り手の顔が感じられます。フェアトレードを知ることは、作り手である開発途上国の人々の暮らしを知ることになり、世界の現状を知ることにも繋がります。だからこそ開発教育という観点からもフェアトレードはとても重要なテーマです。
これからもワクらぼではフェアトレードについてたくさんの人にその仕組みや背景を説明し、国や地域を越えて人々が共に笑い暮らせる世界を願いながら活動していきたいと思っています