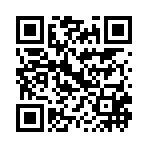2012年02月29日
ワークショップ・雑記①
ワークショップという言葉からどんなイメージが浮かびますか?
今日の日本では‘ワークショップ’と言えば学習会、勉強の場というイメージでしょうか?!
本来のワークショップworkshopという言葉は「作業場」「工房」を意味しますが、体験型学習や講座を概してワークショップと呼んでいますよね。20世紀初頭、アメリカの大学で始まった演劇の体験型講座が、現在用いられているワークショップという言葉の起源のようです。
日本でワークショップという言葉が使われるようになったのは30年位前のことでしょうか?「ワークショップ? 何それ? どんなことをするの?」と初めはその言葉の持つ‘ワーク’と‘ショップ’が結びつかず、全くイメージできない人たちがたくさんいました。時代は流れ、ワークショップという言葉は現代社会においてしっかりその地位を獲得したようです。
日本ではワークショップはかなり広い意味で使われています。演劇や音楽のワークショップもありますし、市民活動や行政の実施する市政講座でのワークショップもあります。ものづくり体験ワークショップというのもよく目にします。
グループに分かれ、話し合いをすること=ワークショップのように捉えられることもあるようですが、ワークショップはもう少し奥の深いところにその面白さがあるのではないでしょうか!
ワークショップについて、思いつくままにあれこれとお伝えしていきたいと思います
今日の日本では‘ワークショップ’と言えば学習会、勉強の場というイメージでしょうか?!
本来のワークショップworkshopという言葉は「作業場」「工房」を意味しますが、体験型学習や講座を概してワークショップと呼んでいますよね。20世紀初頭、アメリカの大学で始まった演劇の体験型講座が、現在用いられているワークショップという言葉の起源のようです。
日本でワークショップという言葉が使われるようになったのは30年位前のことでしょうか?「ワークショップ? 何それ? どんなことをするの?」と初めはその言葉の持つ‘ワーク’と‘ショップ’が結びつかず、全くイメージできない人たちがたくさんいました。時代は流れ、ワークショップという言葉は現代社会においてしっかりその地位を獲得したようです。
日本ではワークショップはかなり広い意味で使われています。演劇や音楽のワークショップもありますし、市民活動や行政の実施する市政講座でのワークショップもあります。ものづくり体験ワークショップというのもよく目にします。
グループに分かれ、話し合いをすること=ワークショップのように捉えられることもあるようですが、ワークショップはもう少し奥の深いところにその面白さがあるのではないでしょうか!
ワークショップについて、思いつくままにあれこれとお伝えしていきたいと思います

2012年02月26日
お金の役割ゲーム・勉強会
 2月23日木曜日の夜、アイセル21の集会室でワークショップの勉強会を開きました。
2月23日木曜日の夜、アイセル21の集会室でワークショップの勉強会を開きました。これはワクらぼメンバーのスキルアップをめざす内部研修会を兼ねております。とはいっても、ワークショップには参加者が必要です。何人かの方にお声かけして参加協力をいただき、ご意見やご感想も聞かせていただきました。
 今回の勉強会、ワークショップのタイトルは「お金の役割カードゲーム」! JCFA(日本消費者金融協会)が製作した金銭教育教材です。物々交換から貨幣経済へ至るお金の成り立ちや役割を、カードを使って楽しみながら学ぶことを目的に作られたものです。当日は、プロミス株式会社静岡お客様サービスプラザの皆様にご協力をいただき、進行役を願いしてワークショップを進めていただきました。
今回の勉強会、ワークショップのタイトルは「お金の役割カードゲーム」! JCFA(日本消費者金融協会)が製作した金銭教育教材です。物々交換から貨幣経済へ至るお金の成り立ちや役割を、カードを使って楽しみながら学ぶことを目的に作られたものです。当日は、プロミス株式会社静岡お客様サービスプラザの皆様にご協力をいただき、進行役を願いしてワークショップを進めていただきました。 このワークショップはゲーム形式で、カードを使って行います。対象は小学生以上。「子ども向けに作られていますよ。」とうかがっていましたが、大人も十分楽しめます。
このワークショップはゲーム形式で、カードを使って行います。対象は小学生以上。「子ども向けに作られていますよ。」とうかがっていましたが、大人も十分楽しめます。 自分で考えること、相手とコミュニケーションをとること、ゲームから何かを感じ取ること、がワークショップの醍醐味ですね。このゲームもそれらの要素を十分備えていました。今回の参加は大人だけでしたが(しかも女性のみ!)参加者それぞれが何かを感じてくれたと思います。
自分で考えること、相手とコミュニケーションをとること、ゲームから何かを感じ取ること、がワークショップの醍醐味ですね。このゲームもそれらの要素を十分備えていました。今回の参加は大人だけでしたが(しかも女性のみ!)参加者それぞれが何かを感じてくれたと思います。「お金の役割カードゲーム」は24年度ワクらぼのイベントとしてちょっとバージョンアップして登場する予定です。楽しみにお待ちください

今回のような新しいワークシップ(ゲームやアクティビティ中心)の勉強会を今後も不定期に開催して参ります。ブログでお知らせして参りますので興味のある方は参加ご協力をお願いいたします。
2012年02月21日
北街道の唄♪♪③
ワクらぼ も応援している「北街道の唄プロジェクト」の活動が、2月20日付けの静岡新聞朝刊に掲載されました。お読みになられた方も多いと思います。
「北街道の唄」や森下さんについてもっと詳しく知りたい方は、
(財)しずおか健康長寿財団『健康いきいき心ときめき』 http://www.kenkouikigai.jp/ の中にある『地域元気活動』 コーナーの記事↓をぜひお読みください
http://www.kenkouikigai.jp/archive/03/03921RLrRPK7OL.asp
「北街道の唄」や森下さんについてもっと詳しく知りたい方は、
(財)しずおか健康長寿財団『健康いきいき心ときめき』 http://www.kenkouikigai.jp/ の中にある『地域元気活動』 コーナーの記事↓をぜひお読みください

http://www.kenkouikigai.jp/archive/03/03921RLrRPK7OL.asp
2012年02月19日
開発教育を考える⑦
開発教育のワークショップや講師派遣などを行っている民間組織はNGOと呼ばれることが多いです。日本でも多くのNGOが開発途上国の貧困や教育格差、生活改善などの問題に取り組んでいます。日本発の団体もありますし、海外の団体の日本支部という形をとって国際的な組織で活動しているところもあります。
NGOは英語のNon-Governmental Organizations(非政府組織)の頭文字をとっています。国家に介入されることなく、政府や政治活動を超えて民間で活動するという意味で非政府という言葉が使われます。国連で使用され、広まった言葉だと言われています。
日本では、国際支援や国際協力をする団体をNGO、国内で活動する団体をNPO(Nonprofit-Organization 非営利団体)と捉える傾向があるようです。
新聞やテレビ、書籍などメディアではNGOという言葉が出てくることが結構あります。ちょっとだけ意識して読んだり聞いたりしてみてください。開発教育がほんの少し身近に感じられるかもしれませんよ
NGOは英語のNon-Governmental Organizations(非政府組織)の頭文字をとっています。国家に介入されることなく、政府や政治活動を超えて民間で活動するという意味で非政府という言葉が使われます。国連で使用され、広まった言葉だと言われています。
日本では、国際支援や国際協力をする団体をNGO、国内で活動する団体をNPO(Nonprofit-Organization 非営利団体)と捉える傾向があるようです。
新聞やテレビ、書籍などメディアではNGOという言葉が出てくることが結構あります。ちょっとだけ意識して読んだり聞いたりしてみてください。開発教育がほんの少し身近に感じられるかもしれませんよ

2012年02月17日
味噌作り体験・記③
 味噌作りの後、参加者みんなでダイラボウに登りました。もちろん歩いても登れますが、味噌作り体験がメインの今回は車で頂上を目指します。一部未舗装部分を除いて道路は整備されていますので頂上まで15分くらいで行くことができます。
味噌作りの後、参加者みんなでダイラボウに登りました。もちろん歩いても登れますが、味噌作り体験がメインの今回は車で頂上を目指します。一部未舗装部分を除いて道路は整備されていますので頂上まで15分くらいで行くことができます。ダイラボウは富厚里(ふこうり)をやさしく包み込む、藁科(わらしな)川中流域にある標高561mの山です。全国各地に残るダイダラボッチ伝説の1つがここにあり、頂上が平らになっているのはダイダラボッチの足跡だと言われています。そのダイラボウからの眺めが壮観!です。
藁科川が流れ、川にはいくつかの橋がかかり、ダイラボウのすぐ真下には第2東名が一直線に続いています。県庁や市役所がある静岡市街を挟んで谷津山や賎機(しずはた)山がこんもり緑の杜を作っています。キラキラと海がひかり、その先には伊豆半島がかすみます。残念ながら富士山だけが雲に隠れていました。まるで風景画のような、本物なのにジオラマのような不思議な眺めでした。とっても素敵なところです。空気の澄んでいる冬のこの時期の眺めが一番だそうですよ。ぜひ一度お出かけください。
 お味噌作りでお世話になった富厚里のさとう農園は富厚里橋を渡ってちょっと広めの通りを左折、‘大きな水車とお店の看板’が目印です。こちらも訪ねてみてくださいね
お味噌作りでお世話になった富厚里のさとう農園は富厚里橋を渡ってちょっと広めの通りを左折、‘大きな水車とお店の看板’が目印です。こちらも訪ねてみてくださいね
2012年02月14日
開発教育を考える⑥
「子どもの権利条約」って知っていますか?
子どもの基本的人権を保障するために定められた条約です。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本が批准したのは1994年です。
「子どもの権利条約」には4つの柱となる権利があります。
「子どもの権利条約」-4つの柱
☆生きる権利
子どもたちは健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、健やかに成長する権利を持っています。
☆守られる権利
子どもたちは、あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られなければなりません。紛争下の子ども、障害をもつ子ども、少数民族の子どもなどは特別に守られる権利を持っています。
☆育つ権利
子どもたちは教育を受ける権利を持っています。また、休んだり遊んだりすること、様々な情報を得、自分の考えや信じることが守られることも、自分らしく成長するためにとても重要です。
☆参加する権利
子どもたちは、自分に関係のある事柄について自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、活動することができます。そのときには、家族や地域社会の一員としてルールを守って行動する義務があります。
開発教育に携わるとき、これらの権利はとても大きな意味を持ちます。世界には搾取や紛争・飢餓によって、健康に生きることのできない子どもたちがたくさんいます。その事実をしっかり受け止めることが必要だと思います。私たちは世界の現実を知らなければなりません。
子どもたちはみな‘生きる権利’を持っていると「子どもの権利条約」は謳っています。そしてその権利は、社会の一員としての義務を伴うというのです。54条からなるこの条約、条約ですから難しいです。でもなかなかおもしろいですよ
子どもの基本的人権を保障するために定められた条約です。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本が批准したのは1994年です。
「子どもの権利条約」には4つの柱となる権利があります。
「子どもの権利条約」-4つの柱
☆生きる権利
子どもたちは健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、健やかに成長する権利を持っています。
☆守られる権利
子どもたちは、あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られなければなりません。紛争下の子ども、障害をもつ子ども、少数民族の子どもなどは特別に守られる権利を持っています。
☆育つ権利
子どもたちは教育を受ける権利を持っています。また、休んだり遊んだりすること、様々な情報を得、自分の考えや信じることが守られることも、自分らしく成長するためにとても重要です。
☆参加する権利
子どもたちは、自分に関係のある事柄について自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、活動することができます。そのときには、家族や地域社会の一員としてルールを守って行動する義務があります。
開発教育に携わるとき、これらの権利はとても大きな意味を持ちます。世界には搾取や紛争・飢餓によって、健康に生きることのできない子どもたちがたくさんいます。その事実をしっかり受け止めることが必要だと思います。私たちは世界の現実を知らなければなりません。
子どもたちはみな‘生きる権利’を持っていると「子どもの権利条約」は謳っています。そしてその権利は、社会の一員としての義務を伴うというのです。54条からなるこの条約、条約ですから難しいです。でもなかなかおもしろいですよ

2012年02月13日
味噌作り体験・記②
味噌作りのような体験講座では、プラスαの楽しみがたまりません。
 さとう農園の佐藤さんが昨年仕込んだお味噌で豚汁を作ってくれました。あったか豚汁はお代りする人続出です。私たちの作るお味噌もこんなにおいしくできるのかしら?!と不安になりつつ、期待も大きく膨らみます。お漬物も佐藤さんの自家製。麹漬の沢庵がほんのり甘くて絶品です。同じ藁科(わらしな)地区・水見色(みずみいろ)“茶どころ かつ山”で水見色茶を販売している勝山さんが、おいしいお水とおいしいお米でふっくらつやつやのおにぎりを作ってくれました。こちらも絶品! 大満足の昼食となりました。
さとう農園の佐藤さんが昨年仕込んだお味噌で豚汁を作ってくれました。あったか豚汁はお代りする人続出です。私たちの作るお味噌もこんなにおいしくできるのかしら?!と不安になりつつ、期待も大きく膨らみます。お漬物も佐藤さんの自家製。麹漬の沢庵がほんのり甘くて絶品です。同じ藁科(わらしな)地区・水見色(みずみいろ)“茶どころ かつ山”で水見色茶を販売している勝山さんが、おいしいお水とおいしいお米でふっくらつやつやのおにぎりを作ってくれました。こちらも絶品! 大満足の昼食となりました。
 静岡の‘北街道’をテーマにした『北街道の唄』、とっても素敵な歌です。味噌作り体験に参加してくださった《北街道の唄プロジェクト》のメンバーが紹介してくれました。
静岡の‘北街道’をテーマにした『北街道の唄』、とっても素敵な歌です。味噌作り体験に参加してくださった《北街道の唄プロジェクト》のメンバーが紹介してくれました。
サビの歌詞、「水の流れ 人の流れ 時は流れ 北街道~♪」を練習して、ギターの伴奏に合わせてみんなで青空コーラス。覚えやすくてホッとするメロディです。ほんとに楽しいひとときでした
 さとう農園の佐藤さんが昨年仕込んだお味噌で豚汁を作ってくれました。あったか豚汁はお代りする人続出です。私たちの作るお味噌もこんなにおいしくできるのかしら?!と不安になりつつ、期待も大きく膨らみます。お漬物も佐藤さんの自家製。麹漬の沢庵がほんのり甘くて絶品です。同じ藁科(わらしな)地区・水見色(みずみいろ)“茶どころ かつ山”で水見色茶を販売している勝山さんが、おいしいお水とおいしいお米でふっくらつやつやのおにぎりを作ってくれました。こちらも絶品! 大満足の昼食となりました。
さとう農園の佐藤さんが昨年仕込んだお味噌で豚汁を作ってくれました。あったか豚汁はお代りする人続出です。私たちの作るお味噌もこんなにおいしくできるのかしら?!と不安になりつつ、期待も大きく膨らみます。お漬物も佐藤さんの自家製。麹漬の沢庵がほんのり甘くて絶品です。同じ藁科(わらしな)地区・水見色(みずみいろ)“茶どころ かつ山”で水見色茶を販売している勝山さんが、おいしいお水とおいしいお米でふっくらつやつやのおにぎりを作ってくれました。こちらも絶品! 大満足の昼食となりました。 静岡の‘北街道’をテーマにした『北街道の唄』、とっても素敵な歌です。味噌作り体験に参加してくださった《北街道の唄プロジェクト》のメンバーが紹介してくれました。
静岡の‘北街道’をテーマにした『北街道の唄』、とっても素敵な歌です。味噌作り体験に参加してくださった《北街道の唄プロジェクト》のメンバーが紹介してくれました。サビの歌詞、「水の流れ 人の流れ 時は流れ 北街道~♪」を練習して、ギターの伴奏に合わせてみんなで青空コーラス。覚えやすくてホッとするメロディです。ほんとに楽しいひとときでした

2012年02月13日
おすすめHP情報②
今回は NPO法人音楽の架け橋・メセナ静岡 をご紹介します。http://www3.hp-ez.com/hp/mesenashizuoka/
「音楽ホールでクラシック音楽などを聴く機会の少ない子どもたちや心身に障害をお持ちの方々、特別支援学校に通う生徒さんたちに、御家族の皆様や介護者の皆さまとご一緒に、音楽ホールで演奏される本物のクラシック音楽を楽しんでいただきたい」との思いから活動を始められ、「企業や個人の皆さまと音楽家を結ぶ架け橋となり音楽を通して地域に貢献」することをめざしていらっしゃいます。
今年5回目の開催を迎える『モーツァルトの優しい調べ』には、毎年小さな子どもからお年寄りまで、障害のあるなしにかかわらず、さまざまな方が音楽を楽しみに集まります。みなさん、生オーケストラの音を心から楽しんでいらっしゃいます。♪音楽♪からのまちづくり、とってもステキな活動です。コンサートボランティア育成プログラムも実施していますよ。
いつかワークショップでコラボできたらうれしいです
「音楽ホールでクラシック音楽などを聴く機会の少ない子どもたちや心身に障害をお持ちの方々、特別支援学校に通う生徒さんたちに、御家族の皆様や介護者の皆さまとご一緒に、音楽ホールで演奏される本物のクラシック音楽を楽しんでいただきたい」との思いから活動を始められ、「企業や個人の皆さまと音楽家を結ぶ架け橋となり音楽を通して地域に貢献」することをめざしていらっしゃいます。
今年5回目の開催を迎える『モーツァルトの優しい調べ』には、毎年小さな子どもからお年寄りまで、障害のあるなしにかかわらず、さまざまな方が音楽を楽しみに集まります。みなさん、生オーケストラの音を心から楽しんでいらっしゃいます。♪音楽♪からのまちづくり、とってもステキな活動です。コンサートボランティア育成プログラムも実施していますよ。
いつかワークショップでコラボできたらうれしいです

2012年02月12日
味噌作り体験・記①
 昨日2月11日、味噌作り体験 at 富厚里(ふこうり) が盛況のうちに無事終了しました。スタッフ、参加者の中に強力な晴れ男・女!がいたらしく(笑)、寒風さらされることもなく冬晴れの最高の一日を皆で楽しむことができました。ご参加いただいた皆様、ご指導いただいた富厚里・さとう農園の佐藤さんと奥さま、本当にありがとうございました。
昨日2月11日、味噌作り体験 at 富厚里(ふこうり) が盛況のうちに無事終了しました。スタッフ、参加者の中に強力な晴れ男・女!がいたらしく(笑)、寒風さらされることもなく冬晴れの最高の一日を皆で楽しむことができました。ご参加いただいた皆様、ご指導いただいた富厚里・さとう農園の佐藤さんと奥さま、本当にありがとうございました。 味噌作りは、米麹をバラバラにして塩と混ぜ、‘塩きり麹’を作るところから始まりました。麹はツンと鼻にくるちょっと尖った麹独特のにおいがあります。手を麹のかたまりの中に入れるとほんのりあったか、麹が生きているのがわかります。
味噌作りは、米麹をバラバラにして塩と混ぜ、‘塩きり麹’を作るところから始まりました。麹はツンと鼻にくるちょっと尖った麹独特のにおいがあります。手を麹のかたまりの中に入れるとほんのりあったか、麹が生きているのがわかります。 それに塩をまんべんなく混ぜると、尖ったにおいがやさしいにおいに変わるのがとっても不思議でした。
それに塩をまんべんなく混ぜると、尖ったにおいがやさしいにおいに変わるのがとっても不思議でした。 大豆は前の日から水に浸した(この作業は佐藤さんがしてくださいました)ものを、釜でグツグツ、柔らかくなるまで茹でます。昔ながらの、マキを使っての作業。煙が目にしみます。茹でた大豆は熱いうちに臼と杵でつぶします。大豆の形がちょっぴり残るくらいのつぶし加減が佐藤流。茹でた大豆はそのまま味見しても甘くてとってもおいしかったですよ。
大豆は前の日から水に浸した(この作業は佐藤さんがしてくださいました)ものを、釜でグツグツ、柔らかくなるまで茹でます。昔ながらの、マキを使っての作業。煙が目にしみます。茹でた大豆は熱いうちに臼と杵でつぶします。大豆の形がちょっぴり残るくらいのつぶし加減が佐藤流。茹でた大豆はそのまま味見しても甘くてとってもおいしかったですよ。つぶした大豆が冷めたら‘塩きり麹’としっかり混ぜて、ソフトボールくらいのお団子にします。それを樽にパイ投げみたいに思いっきり投げ込んでビチャッと空気抜き。まんべんなく平らに詰めたら、また投げ込んで…樽一杯になるまでがんばりました。
 ビニールをかぶせ密閉して重しのふたをしたら出来上がり。後は麹の力で熟成されるのを待つだけです。どんなお味噌ができるのでしょう? ワクワクドキドキ、楽しみです。
ビニールをかぶせ密閉して重しのふたをしたら出来上がり。後は麹の力で熟成されるのを待つだけです。どんなお味噌ができるのでしょう? ワクワクドキドキ、楽しみです。大豆15㎏、麹15kg、塩6kgが樽1つ分の味噌の材料。2グループに分かれて2樽作り、合計100kgの味噌ができました

2012年02月07日
HUG後記③
昨年12月15日に静岡市番町市民活動センターで開催したHUG(避難所運営ゲーム)ワークショップの様子を、(財)しずおか健康長寿財団が運営するHP「健康いきいき心ときめき」で紹介していただきました。生きがい特派員の方の取材記事です。HUGの様子がとてもよくわかります。是非お読みください!
「健康いきいき心ときめき」(財団法人 しずおか健康長寿財団)のhttp://www.kenkouikigai.jp/
「地域耳寄り情報」のコーナーに載っています
http://www.kenkouikigai.jp/archive/02/0291QSTGA5LQQ2.asp
※財団法人しずおか健康長寿財団は、21世紀の高齢社会に対応する新たな社会づくりの推進母体として設立され、シニアが健康に心豊かに暮らしていくための様々な情報をHPで発信しています。
「健康いきいき心ときめき」(財団法人 しずおか健康長寿財団)のhttp://www.kenkouikigai.jp/
「地域耳寄り情報」のコーナーに載っています

http://www.kenkouikigai.jp/archive/02/0291QSTGA5LQQ2.asp
※財団法人しずおか健康長寿財団は、21世紀の高齢社会に対応する新たな社会づくりの推進母体として設立され、シニアが健康に心豊かに暮らしていくための様々な情報をHPで発信しています。