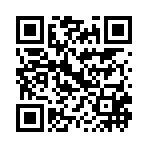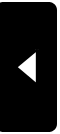2013年03月24日
ご紹介・知花くららさんのエチオピア紀行
 モデルとして活躍されている知花くららさんは国連WFP(世界食糧計画)のオフィシャルサポーターを務めています。
モデルとして活躍されている知花くららさんは国連WFP(世界食糧計画)のオフィシャルサポーターを務めています。
国連WFPでは赤いカップを目印に、レッドカップキャンペーンを展開しています。開発途上国の子どもたちが給食で栄養を補い、学校に通えるようサポートする活動です。
地花さんは国連WFPの活動を視察するためにエチオピアを訪れ、母子栄養支援プログラムや学校給食プログラムの様子を視察しました。
その様子がテレビ番組「知花くらら アフリカ紀行~エチオピアの夢とミライ~」として先日放映されました。今回フェイスブック上にアップされ、何回かに分けてみることができます。
アフリカの子どもたちの置かれている教育現状や子どもたちの様子が映し出され、日本では考えられない現実が見えてきます。
でも、子どもたちは明るく、たくさんの夢を持っています。夢は希望となり、未来を切り開く力となることでしょう。
その第1回分がこちらです。ぜひご覧ください

https://www.facebook.com/photo.php?v=412896002139674
2013年02月23日
フェアトレードのチョコレート
 コンビニでフェアトレードのチョコレートを見つけました。
コンビニでフェアトレードのチョコレートを見つけました。オーストラリア・キャドバリー社のミルクチョコレート。
キャドバリーでは、自社のミルクチョコレートをすべてフェアトレード商品にすると決め、販売しています。このことが、オーストラリアでの年間一人当たりのフェアトレード購入額アップの要因の1つにもなったと、以前フェアトレードショップテーボムの今井さんから教えてもらいました。
 そのフェアトレードチョコレートがコンビニの棚にほかのチョコレートと一緒に並んでいました。ほかのチョコレートと違うのはフェアトレードのラベルがついていること。
そのフェアトレードチョコレートがコンビニの棚にほかのチョコレートと一緒に並んでいました。ほかのチョコレートと違うのはフェアトレードのラベルがついていること。こんな風にフェアトレード商品が気軽に買えるようになるのは素敵なことですね。
開発教育では、経済的に貧しい国の現状を伝え、途上国の人々が生活の糧を得るための1つのモデルとしてフェアトレードを紹介します。なぜフェアトレード(公正貿易)が必要なのか? フェアとはどういうことなのか? 途上国・先進国それぞれができることは何なのか?
一人でも多くの子どもたちが学校に通い、健康に育ち、大人になって仕事につくために、どのようなことが必要なのでしょう? そもそも世界ではどのくらいの子どもたちが学校に通えず、読み書きができず、家のため家族のために労働させられているのでしょう?
フェアトレードのチョコレートを手に、いろんなことを考えました。
もしフェアトレードラベルを見かけたら、ほんのちょっとだけ世界のことを考える時間を心の中に持っていただけたら、と思います


2013年02月15日
ハンガーマップ2012
以前ご紹介したハンガーマップ
→ http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e878416.html
 その最新版が国連WFPウェブサイトで見られるようになりました。
その最新版が国連WFPウェブサイトで見られるようになりました。
『世界の飢餓状況2012』
これは、国連WFPが、「世界の食糧不安の現状2012」(国際連合食糧農業機関(FAO)、国際農業開発基金(IFAD)、国連WFP 発行)の統計に基づき作成したものです。
現在、8億7千万人の人が飢餓に苦しんでいます。これは世界の総人口から考えると8人に1人の割合になります。そして飢餓に苦しむ人の98%が途上国で暮らしています。
以前のご紹介では飢餓に苦しむ人の数は9億2500万人、7人に1人とお伝えしました。
ほんの少しだけ状況は改善されたのでしょうか? この数字が少しでも小さくなることを願っています。
WFPのHP、「数字で見る飢餓」をぜひご覧ください
→ http://ja.wfp.org/hunger-jp/stats
→ http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e878416.html
 その最新版が国連WFPウェブサイトで見られるようになりました。
その最新版が国連WFPウェブサイトで見られるようになりました。『世界の飢餓状況2012』
これは、国連WFPが、「世界の食糧不安の現状2012」(国際連合食糧農業機関(FAO)、国際農業開発基金(IFAD)、国連WFP 発行)の統計に基づき作成したものです。
現在、8億7千万人の人が飢餓に苦しんでいます。これは世界の総人口から考えると8人に1人の割合になります。そして飢餓に苦しむ人の98%が途上国で暮らしています。
以前のご紹介では飢餓に苦しむ人の数は9億2500万人、7人に1人とお伝えしました。
ほんの少しだけ状況は改善されたのでしょうか? この数字が少しでも小さくなることを願っています。
WFPのHP、「数字で見る飢餓」をぜひご覧ください

→ http://ja.wfp.org/hunger-jp/stats
2013年01月13日
現状・食品ロス
11日にAFPから配信された記事です。ネットのトップ記事でご覧になった方も多いのでは…?
世界の食料の最大半分がごみに、英団体が警鐘
AFP=時事 1月11日(金)12時13分配信
【AFP=時事】英国の機械技術者協会(Institution of Mechanical Engineers)は10日、世界で生産される食料のうち、最大で約半分に当たる20億トンもの量が廃棄されているとの報告書を発表した。
肥満人口が栄養不足人口を上回る、赤十字社2011年報告書
報告書「Global Food; Waste Not, Want Not(世界の食料:廃棄を減らし、欲するのをやめよう)」によると、世界で年間40億トン生産される食料のうち、3~5割が消費されずに捨てられている。
廃棄の原因は発展途上国でのインフラや貯蔵施設の不足、先進国での「1個買えばもう1個無料」キャンペーンや消費者のこだわりにあるという。
廃棄量が最も多い国の1つは英国で、生産される野菜の約3割が「形が悪い」ためスーパーが買い取らないという理由で収穫されていない。また、欧州と米国の消費者が購入する食料のうち半分が捨てられているという。
同協会のエネルギー・環境部門を率いるティム・フォックス(Tim Fox)氏は「これ(廃棄食料)は増加を続ける世界人口を支えたり、飢餓に苦しむ人々に与えたりできるはずの食料だ」と述べるとともに、食料の生産・加工・配送といった過程で使われる土地や水、エネルギー資源が無駄になっていることも指摘した。【翻訳編集】 AFPBB News
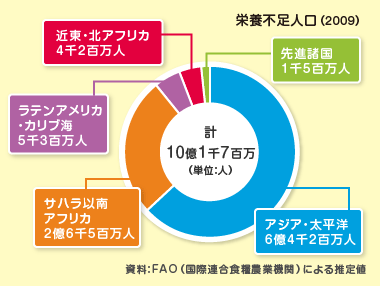
世界では約10億の人が栄養不足で苦しんでいます。
平成21年の食糧援助総量は世界で570万トン。その一方で、日本が廃棄している食糧は年間500万~800万トンにのぼります。食糧援助と同量以上の食糧を私たちは食品ロス(=食べられるにもかかわらず、廃棄されているもの)として廃棄しているのです。
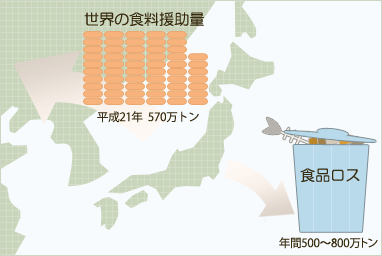
日本がこの食品ロスをなくせば世界の食糧事情がよくなる、という単純な問題ではありません。でも、この問題は私たちが「食」を考えるための大切なポイントとなるはずです。
現在もこの地球上で、飢えと貧困が原因で毎日2万5000人近くが命を落としています。このような世界の現状を皆さんに知ってもらうことをめざして開発教育という分野があります。
「知る」ことが力になる、そんな活動もあります。
世界の食料の最大半分がごみに、英団体が警鐘
AFP=時事 1月11日(金)12時13分配信
【AFP=時事】英国の機械技術者協会(Institution of Mechanical Engineers)は10日、世界で生産される食料のうち、最大で約半分に当たる20億トンもの量が廃棄されているとの報告書を発表した。
肥満人口が栄養不足人口を上回る、赤十字社2011年報告書
報告書「Global Food; Waste Not, Want Not(世界の食料:廃棄を減らし、欲するのをやめよう)」によると、世界で年間40億トン生産される食料のうち、3~5割が消費されずに捨てられている。
廃棄の原因は発展途上国でのインフラや貯蔵施設の不足、先進国での「1個買えばもう1個無料」キャンペーンや消費者のこだわりにあるという。
廃棄量が最も多い国の1つは英国で、生産される野菜の約3割が「形が悪い」ためスーパーが買い取らないという理由で収穫されていない。また、欧州と米国の消費者が購入する食料のうち半分が捨てられているという。
同協会のエネルギー・環境部門を率いるティム・フォックス(Tim Fox)氏は「これ(廃棄食料)は増加を続ける世界人口を支えたり、飢餓に苦しむ人々に与えたりできるはずの食料だ」と述べるとともに、食料の生産・加工・配送といった過程で使われる土地や水、エネルギー資源が無駄になっていることも指摘した。【翻訳編集】 AFPBB News
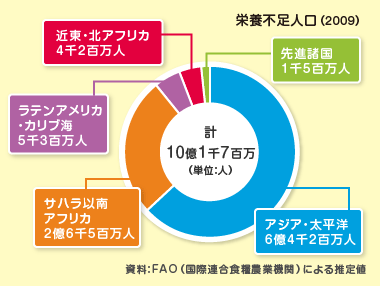
世界では約10億の人が栄養不足で苦しんでいます。
平成21年の食糧援助総量は世界で570万トン。その一方で、日本が廃棄している食糧は年間500万~800万トンにのぼります。食糧援助と同量以上の食糧を私たちは食品ロス(=食べられるにもかかわらず、廃棄されているもの)として廃棄しているのです。
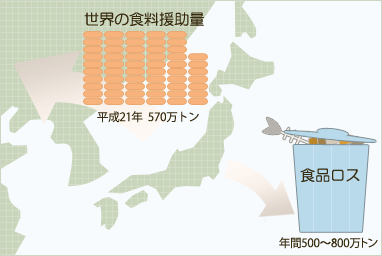
日本がこの食品ロスをなくせば世界の食糧事情がよくなる、という単純な問題ではありません。でも、この問題は私たちが「食」を考えるための大切なポイントとなるはずです。
現在もこの地球上で、飢えと貧困が原因で毎日2万5000人近くが命を落としています。このような世界の現状を皆さんに知ってもらうことをめざして開発教育という分野があります。
「知る」ことが力になる、そんな活動もあります。
2012年11月11日
紹介・国際理解の入門書
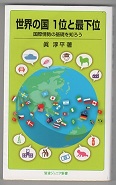
岩波ジュニア新書から国際理解の入門書をご紹介します。
『世界の国 1位と最下位
国際情勢の基礎を知ろう 』
著者は 眞 淳平氏(2010年第1版発行)
岩波ジュニア新書は(何度かご紹介させていただきましたが)、名前の通りジュニア(中学・高校生)対象の新書です。新書として様々な分野をテーマに出版されています。ジュニア対象ですが、専門分野の入門書としては、大人も十分に参考になる書籍だと思います。
今回ご紹介する『世界の国 1位と最下位』は、「世界で最も人口が少ない国は?最も多い国は?」「最も面積の大きい国は?小さい国は?」など、私たちの身近な問題から始まって、食糧自給率や軍事力、貧困率や進学率まで「人口」「経済・政治」「社会」とテーマを3つに分けて解説してくれます。言葉の定義や解説もわかりやすく示してくれているので、今までなんとなくわかっていたことを、きちんと理解するのにとても参考になりますよ。
副題にもあるように「国際情勢の基礎」を知る導入書として優れた本だと思います。
実は開発教育では、この本で述べられているようなことを、ワークショップや講座、キャンペーンなどを通して‘格差’という視点から皆さんにお伝えしているのです。
「国際情勢」なんて言葉を使うとなんだか難しそうですが、世界のことを知ってみようと軽い気持ちで手にとっても十分楽しめる本です。
一度本屋さんや図書館で探してみてくださいね

2012年10月27日
マララさんから思うこと
パキスタンでマララさんという少女が襲撃され、治療のためイギリスに渡ったことがメディアで報じられました。手術は成功し少しずつ回復に向かっているようです。→
http://www.unicef.or.jp/children/children_now/pakistan/sek_pa22.html
http://www.cnn.co.jp/world/35023103.html
彼女が訴えていたのは女の子が教育を受ける権利・
「勉強したい」という思いです。
日本では当たり前の「学校に行くこと、文字や計算を学ぶこと」が当たり前でない国や地域がまだまだあります。特に女の子は、一家の担い手としての男の子に比べて学ぶ機会を与えられず、家事や労働にほとんどの時間を費やさなければならないことが多いようです。
日本で暮らす私たちにはちょっと想像のできない現実があります。
文化や生活習慣の違いは人々の暮らしにいろいろな形で現れます。国や地域によって経済状況も異なります。日本や先進諸国では容易に可能なことも、開発途上国では様々な困難を克服しなければ実現できないことが多いのです。
「学ぶこと」(教育などを受けること)は以前このブログでご紹介したように『子どもの権利条約』に謳われている子どもとしての権利です。
一人でも多くの子どもがその権利を堂々と行使できるよう、私たちができることは何だろうと考えます。開発教育のそれは「伝えること」だと思っています。現場の生の声、映画や書籍、データや情報など、ご紹介できることはたくさんありあそうです。もちろんワークショップも!
今日はマララさんの悲しい事件に関連して『国際ガールズ・デー』を取り上げたNHKのHPをご紹介します。
ぜひご一読を
→ http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/450/134767.html
http://www.unicef.or.jp/children/children_now/pakistan/sek_pa22.html
http://www.cnn.co.jp/world/35023103.html
彼女が訴えていたのは女の子が教育を受ける権利・
「勉強したい」という思いです。
日本では当たり前の「学校に行くこと、文字や計算を学ぶこと」が当たり前でない国や地域がまだまだあります。特に女の子は、一家の担い手としての男の子に比べて学ぶ機会を与えられず、家事や労働にほとんどの時間を費やさなければならないことが多いようです。
日本で暮らす私たちにはちょっと想像のできない現実があります。
文化や生活習慣の違いは人々の暮らしにいろいろな形で現れます。国や地域によって経済状況も異なります。日本や先進諸国では容易に可能なことも、開発途上国では様々な困難を克服しなければ実現できないことが多いのです。
「学ぶこと」(教育などを受けること)は以前このブログでご紹介したように『子どもの権利条約』に謳われている子どもとしての権利です。
一人でも多くの子どもがその権利を堂々と行使できるよう、私たちができることは何だろうと考えます。開発教育のそれは「伝えること」だと思っています。現場の生の声、映画や書籍、データや情報など、ご紹介できることはたくさんありあそうです。もちろんワークショップも!
今日はマララさんの悲しい事件に関連して『国際ガールズ・デー』を取り上げたNHKのHPをご紹介します。
ぜひご一読を

→ http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/450/134767.html
2012年10月20日
『世界手洗いの日』の出来事

 10月15日アイセル21で高島和音さんによる活動報告会が開催されました。ドミニカ共和国、東ティモール、ハイチなどで医療支援活動を続けてこられた高島さんの生の声と彼女が撮影した写真の数々は、支援活動の必要性と、支援活動を続けられている人々の努力が直接伝わってくるものでした。日本では考えられない状況を生きる人々の暮らしがそこにはあります。
10月15日アイセル21で高島和音さんによる活動報告会が開催されました。ドミニカ共和国、東ティモール、ハイチなどで医療支援活動を続けてこられた高島さんの生の声と彼女が撮影した写真の数々は、支援活動の必要性と、支援活動を続けられている人々の努力が直接伝わってくるものでした。日本では考えられない状況を生きる人々の暮らしがそこにはあります。 厳しい現実の中、明るくたくましく日常を送るドミニカや東ティモールの人々。
厳しい現実の中、明るくたくましく日常を送るドミニカや東ティモールの人々。大地震でめちゃめちゃになったハイチの街並み。懸命に支援するNGOや国連スタッフ。課題や様々な問題も含めて、報道では伝わらない世界の姿を教えてもらった気がしました。
偶然にも、10月15日は『世界手洗いの日』です。高島さんの活動の中心が保健衛生であったとうかがい、改めてトイレや清潔な水のことを考えさせられました。
『世界手洗いの日』がどんな目的で作られたかというと…
世界で、5歳の誕生日を迎えずに、命を終える子どもたちは年間760万人。その原因の多くは、予防可能な病気です。
私たちの生活には、当たり前にある水やトイレ、そして食事・・・ それらが不足しているために、不衛生な環境や生活習慣を強いられ、下痢や肺炎にかかって命を失う子どもたちが220万人もいます。
もし、せっけんを使って、正しく手を洗うことができたら。 年間100万人もの子どもの命が守られ、また、下痢によって学校を休まなければいけない子どもたちが大幅に減ります。
自分の体を病気から守る、最もシンプルな方法のひとつが、せっけんを使った手洗いです。
正しい手洗いを広めるため、国際衛生年であった2008年に、毎年10月15日が「世界手洗いの日」(Global Handwashing Day)と定められました。 (~日本ユニセフ協会HPより~)
開発途上国では、不衛生な生活環境から下痢や肺炎にかかって命を落とす子どもたちがまだたくさんいます。「手を洗う」という簡単な行為が子どもたちの命を守る手立ての1つになるのであれば、声を上げて広く訴えていきたいと思います

2012年10月05日
池上彰氏の国際貢献NET講座
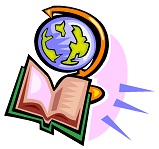 開発教育では、開発途上国での様々な問題を取り上げて皆さんにお伝えします。経済、教育、産業、健康、本当にいろいろな角度から、考え、感じ、学ぶことがたくさんあります。
開発教育では、開発途上国での様々な問題を取り上げて皆さんにお伝えします。経済、教育、産業、健康、本当にいろいろな角度から、考え、感じ、学ぶことがたくさんあります。 今日ご紹介するのは、フリージャーナリストの池上彰氏が
今日ご紹介するのは、フリージャーナリストの池上彰氏がナビゲーターとなり、様々な分野で活躍されている方とインタビュー形式で世界の問題をわかりやすく伝えている
JICAの『池上彰と考える!
ビジネスパーソンの「国際貢献」入門』です。
http://www.jica.go.jp/aboutoda/ikegami/index.html
読み応えたっぷりの内容です。
ぜひ、興味のあるテーマからお読みください。
 10月8日 JICAボランティア帰国報告会が
10月8日 JICAボランティア帰国報告会が静岡県庁別館で開催されます。
こちらは実施にボランティアの生の声が聞けますよ

→http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e934440.html
2012年09月27日
開発教育を考える⑯
10月17日は国際連合(UNITED NATIONS)で定められた
『貧困撲滅の国際デー』です。
NGO(フランスを拠点とする「国際運動ATD第4世界」の発案により)が多くの国で10月17日を「極貧に打ち克つための世界デー」として記念してきたことを歓迎し、1992年、国連総会はこの日を「貧困撲滅のための国際デー」とすることを宣言しました(12月22日の決議47/196)。この国際デーの狙いは、あらゆる国々、特に開発途上国において、開発の最重要課題である貧困撲滅の必要性を広く知ってもらうことにあります。(~国際連合広報センターHP~)
STAND UP TAKE ACTIONキャンペーンでは『世界貧困デー』と呼んでいます。逆の発想から『世界反貧困デー』といわれることもあります。いずれにしても、貧困に立ち向かい、貧困のない世界を作るようみんなで頑張ろう、という思いから生まれた国際デーだと思います。
では、何を基準に「貧困」ととらえるのでしょうか? 「貧困」を表す指標にはいろいろなものがあります。その1つとして、1日2ドル(およそ180円)未満で暮らす人を「貧困」であると考え、その割合がその国の人口のどのくらいに当たるか(貧困率)を考えてみます。2008年に世界銀行が出した資料でみると、その割合が一番大きいのは、タンザニアで96.6%! つまり、この国のほとんどの人が1日2ドル未満で暮らしているということになります。1日1.25ドル未満で暮らす人は88.5%にもなります。ドルの価値や物価水準は国によって異なるでしょうが、豊かな暮らしを享受できていない人が非常に多いことはこの数字からも明らかです。
同じ資料で、1日2ドル未満で暮らす人口の割合が60%を越える国は38ヶ国あり、そのうちの29ヶ国がアフリカ、サハラ砂漠以南にあります。
「貧困」は21世紀を生きる私たちにとって避けては通れない問題となりました。グローバル化は「貧困」問題に多様化を与えたように思います。経済、教育、文化と様々な分野で格差が生まれ、それが「貧困」と結びついています。精神的(こころの)「貧困」と呼べるものも生まれています。これらの問題と如何に向き合うかが開発教育の分野でも問われます。
確かに深刻な問題ですが、あまり身構えず、たくさんの人に知ってもらえたらいいなと思っています。STAND UP TAKE ACTIONのキャンペーンにもそんな思いから参加します。
まず大切なのは「伝える」ことだと考え、「知る」「気づく」 ‘きっかけ作り’を続けていこうと思います
『貧困撲滅の国際デー』です。
NGO(フランスを拠点とする「国際運動ATD第4世界」の発案により)が多くの国で10月17日を「極貧に打ち克つための世界デー」として記念してきたことを歓迎し、1992年、国連総会はこの日を「貧困撲滅のための国際デー」とすることを宣言しました(12月22日の決議47/196)。この国際デーの狙いは、あらゆる国々、特に開発途上国において、開発の最重要課題である貧困撲滅の必要性を広く知ってもらうことにあります。(~国際連合広報センターHP~)
STAND UP TAKE ACTIONキャンペーンでは『世界貧困デー』と呼んでいます。逆の発想から『世界反貧困デー』といわれることもあります。いずれにしても、貧困に立ち向かい、貧困のない世界を作るようみんなで頑張ろう、という思いから生まれた国際デーだと思います。
では、何を基準に「貧困」ととらえるのでしょうか? 「貧困」を表す指標にはいろいろなものがあります。その1つとして、1日2ドル(およそ180円)未満で暮らす人を「貧困」であると考え、その割合がその国の人口のどのくらいに当たるか(貧困率)を考えてみます。2008年に世界銀行が出した資料でみると、その割合が一番大きいのは、タンザニアで96.6%! つまり、この国のほとんどの人が1日2ドル未満で暮らしているということになります。1日1.25ドル未満で暮らす人は88.5%にもなります。ドルの価値や物価水準は国によって異なるでしょうが、豊かな暮らしを享受できていない人が非常に多いことはこの数字からも明らかです。
同じ資料で、1日2ドル未満で暮らす人口の割合が60%を越える国は38ヶ国あり、そのうちの29ヶ国がアフリカ、サハラ砂漠以南にあります。
「貧困」は21世紀を生きる私たちにとって避けては通れない問題となりました。グローバル化は「貧困」問題に多様化を与えたように思います。経済、教育、文化と様々な分野で格差が生まれ、それが「貧困」と結びついています。精神的(こころの)「貧困」と呼べるものも生まれています。これらの問題と如何に向き合うかが開発教育の分野でも問われます。
確かに深刻な問題ですが、あまり身構えず、たくさんの人に知ってもらえたらいいなと思っています。STAND UP TAKE ACTIONのキャンペーンにもそんな思いから参加します。
まず大切なのは「伝える」ことだと考え、「知る」「気づく」 ‘きっかけ作り’を続けていこうと思います

2012年08月31日
ザンビア・WFP写真紹介

WFP国連世界食糧計画のオフィシャルサポーターをつとめている知花くららさんが4年前にアフリカのザンビアを訪れた時の写真展
『知花くららが見たザンビア~hope~』をインターネットで見ることができます。
→http://www.wfp.or.jp/press/pdf/WFP_Photo_Exhibition_2008.pdf
飢餓にまつわる問題やWFPの活動紹介がメインですが、ザンビアの現状を画像として見ることができます。添えられている説明文もわかりやすく、ぜひ見ていただきたいと思います。洪水や干ばつなどの自然災害に加えHIVの感染拡大などアフリカを取り巻く問題は深刻です。

私たちに何ができるのかを考えることは大切です。同じように、何が起きているのかを知ることもとても大切だと考えます。開発教育のスタートはそこにあると思っています。
〈知ること〉で一人ひとりの中に一滴の想いが生まれればいいなと願います。その滴はやがて仲間を作って小さな流れとなり、川となり、海のように深く大きな想いに育つのではないでしょうか?!〈知ること〉が〈考えること〉に、そして〈動き出すこと〉につながるように少しずつ発信を続けます