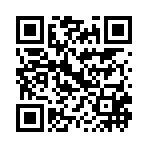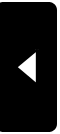2012年08月12日
1L for 10L・水と未来
暑い夏、水分補給は欠かせませんね。今年も“1L for 10L”(ワンリッッター フォー テンリッター)プログラムが実施されています。これはフランスの企業Volvic(ヴォルビック)とUNICEF(ユニセフ)のタイアップキャンペーンです。
 今年で6年目を迎えるこのキャンペーンは、Volvicのミネラルウォーターを買うと売り上げの一部がユニセフに寄付され、ユニセフがアフリカに井戸を新設、10年間のメンテナンスを行うというものです。商品1ℓを買うことで、10年間のメンテナンス期間も含め10ℓの清潔で安全な水が誕生します。これまでの5年間で約30億ℓの清潔で安全な水を供給するための支援が実現しました。
今年で6年目を迎えるこのキャンペーンは、Volvicのミネラルウォーターを買うと売り上げの一部がユニセフに寄付され、ユニセフがアフリカに井戸を新設、10年間のメンテナンスを行うというものです。商品1ℓを買うことで、10年間のメンテナンス期間も含め10ℓの清潔で安全な水が誕生します。これまでの5年間で約30億ℓの清潔で安全な水を供給するための支援が実現しました。
今年のプログラム期間は 7月1日から9月30日まで。
アフリカのマリ共和国でのユニセフ・水プロジェクトに支援されます。
詳しくはこちら→http://www.unicef.or.jp/partner/event/volvic/
マリ共和国はここですよ↓

『世界子供白書2012』によると

マリ共和国では、清潔で安全な水を利用できる人が農村部では約2.2人に1人にとどまっており、半数以上の人は沼や池などの水、人手で掘った浅い井戸の水を使用して生活しています。これらの不衛生な水は、下痢やメジナ虫病、 コレラやトラコマ(慢性結膜炎)を引き起こし、子どもたちの命を危険にさらします。 5歳未満児死亡率が、出生1000人あたり178人(世界で2番目)*と高いマリでは、清潔で安全な水さえあれば予防できる下痢が、子どもの死亡原因の3番目、約18%を占めています。
日本で暮らしていると、蛇口をひねれば安全で清潔な水道水を手軽に飲むことができます。おいしい地下水を飲めるところもたくさん残っています。だからこそ、私たちが忘れがちな水の大切さを考える時間をちょっとだけ持ってくださればうれしいです
 今年で6年目を迎えるこのキャンペーンは、Volvicのミネラルウォーターを買うと売り上げの一部がユニセフに寄付され、ユニセフがアフリカに井戸を新設、10年間のメンテナンスを行うというものです。商品1ℓを買うことで、10年間のメンテナンス期間も含め10ℓの清潔で安全な水が誕生します。これまでの5年間で約30億ℓの清潔で安全な水を供給するための支援が実現しました。
今年で6年目を迎えるこのキャンペーンは、Volvicのミネラルウォーターを買うと売り上げの一部がユニセフに寄付され、ユニセフがアフリカに井戸を新設、10年間のメンテナンスを行うというものです。商品1ℓを買うことで、10年間のメンテナンス期間も含め10ℓの清潔で安全な水が誕生します。これまでの5年間で約30億ℓの清潔で安全な水を供給するための支援が実現しました。今年のプログラム期間は 7月1日から9月30日まで。
アフリカのマリ共和国でのユニセフ・水プロジェクトに支援されます。
詳しくはこちら→http://www.unicef.or.jp/partner/event/volvic/
マリ共和国はここですよ↓

『世界子供白書2012』によると

マリ共和国では、清潔で安全な水を利用できる人が農村部では約2.2人に1人にとどまっており、半数以上の人は沼や池などの水、人手で掘った浅い井戸の水を使用して生活しています。これらの不衛生な水は、下痢やメジナ虫病、 コレラやトラコマ(慢性結膜炎)を引き起こし、子どもたちの命を危険にさらします。 5歳未満児死亡率が、出生1000人あたり178人(世界で2番目)*と高いマリでは、清潔で安全な水さえあれば予防できる下痢が、子どもの死亡原因の3番目、約18%を占めています。
日本で暮らしていると、蛇口をひねれば安全で清潔な水道水を手軽に飲むことができます。おいしい地下水を飲めるところもたくさん残っています。だからこそ、私たちが忘れがちな水の大切さを考える時間をちょっとだけ持ってくださればうれしいです

2012年07月25日
ムヒカ大統領の演説
2012年6月20日から22日にかけてブラジルのリオデジャネイロで開催された
『国連持続可能な開発会議』(リオ+20)
ウルグアイのムヒカ大統領のスピーチをご紹介します。
http://hana.bi/2012/07/mujica-speech-nihongo/
‘持続可能な開発’とは何なのか? 考えさせられます。
皆が自分の問題として考えることであり、大統領の投げかけへの答えは1つではないと思います。
ウルグアイがどこにあるのか、まずそんなところから始めてみませんか?
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/latinamerica.html
日本からは遠く離れた国の、でも同じ地球に暮らすものとして、思いは複雑です
『国連持続可能な開発会議』(リオ+20)
ウルグアイのムヒカ大統領のスピーチをご紹介します。
http://hana.bi/2012/07/mujica-speech-nihongo/
‘持続可能な開発’とは何なのか? 考えさせられます。
皆が自分の問題として考えることであり、大統領の投げかけへの答えは1つではないと思います。
ウルグアイがどこにあるのか、まずそんなところから始めてみませんか?
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/latinamerica.html
日本からは遠く離れた国の、でも同じ地球に暮らすものとして、思いは複雑です

2012年07月20日
開発教育を考える⑭
「難民」という言葉を一度は聞いたことがありますよね。
「難民」は、1951年に国連で採択された『難民の地位に関する条約』で以下のように定義づけられています。
「人権、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受ける恐れがあるために他国に逃れた」人々。
これに対して、自国を出ずに、自国の中で避難生活を強いられている人々を「国内避難民」といいます。「難民」と「国内避難民」とは、正式には使い分けがされています。メディア等の報道で「難民」といわれる場合、彼らは国外に避難した人々です。
紛争や内戦、自然災害などで、とるものもとりあえず命からがら逃れるため、人々は何日もかけて歩いて国境を越え自国から隣国へと移動することが多いです。難民たちを収容するために難民キャンプと呼ばれるものが作られます。逃れてきた難民を保護、収容する施設です。一斉に多くの人々が避難してきた場合、それを受け入れる側にも限界があります。国連を初め、様々な機関やNGOなどが援助の手を差しのべますが、施設の環境は厳しいものです。そしてその厳しい環境で多く犠牲になるのは、弱いもの(子どもやお年寄り)です。
“国境なき医師団”が作成した『難民キャンプへ』(Virtual Tour of a Refugee Camp)をご紹介します。http://www.msf.or.jp/com/camp/index.html
シリアの国内情勢が厳しさを増しています。たくさんの難民が隣国レバノンに逃れているというニュースが流れています。このような現実に目を向け、今世界でどのようなことが起こっているのかを知ること・考えることは、開発教育ではとても大切なことだと思います。知ること・考えることで何が変わるのか? 何も変わらないかもしれない…と思いつつ、でもやはり知ることは重要だと思うのです。そこに開発教育の意義があるのではと願いつつ、開発教育に取り組みたいと考えています
「難民」は、1951年に国連で採択された『難民の地位に関する条約』で以下のように定義づけられています。
「人権、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受ける恐れがあるために他国に逃れた」人々。
これに対して、自国を出ずに、自国の中で避難生活を強いられている人々を「国内避難民」といいます。「難民」と「国内避難民」とは、正式には使い分けがされています。メディア等の報道で「難民」といわれる場合、彼らは国外に避難した人々です。
紛争や内戦、自然災害などで、とるものもとりあえず命からがら逃れるため、人々は何日もかけて歩いて国境を越え自国から隣国へと移動することが多いです。難民たちを収容するために難民キャンプと呼ばれるものが作られます。逃れてきた難民を保護、収容する施設です。一斉に多くの人々が避難してきた場合、それを受け入れる側にも限界があります。国連を初め、様々な機関やNGOなどが援助の手を差しのべますが、施設の環境は厳しいものです。そしてその厳しい環境で多く犠牲になるのは、弱いもの(子どもやお年寄り)です。
“国境なき医師団”が作成した『難民キャンプへ』(Virtual Tour of a Refugee Camp)をご紹介します。http://www.msf.or.jp/com/camp/index.html
シリアの国内情勢が厳しさを増しています。たくさんの難民が隣国レバノンに逃れているというニュースが流れています。このような現実に目を向け、今世界でどのようなことが起こっているのかを知ること・考えることは、開発教育ではとても大切なことだと思います。知ること・考えることで何が変わるのか? 何も変わらないかもしれない…と思いつつ、でもやはり知ることは重要だと思うのです。そこに開発教育の意義があるのではと願いつつ、開発教育に取り組みたいと考えています

2012年07月13日
開発教育研究集会
開発教育を学んでみたい人、のぞいてみたい人、感じてみたい人の勉強会です。
主催するのは
特定非営利活動法人 開発教育協会/DEAR
東京開催なのがちょっと残念ですが、暑い夏を「学びと出会いの夏」に変えてみませんか?
■第30回「開発教育全国研究集会」参加者募集スタート!
■8月4日(土)・5日(日)にJICA地球ひろば(東京・広尾)で開催
--------------------------------------------------------------------------------
■http://www.dear.or.jp/zenken2012/
■http://www.facebook.com/zenken2012
--------------------------------------------------------------------------------
日本ではじめて開発教育が紹介されてから30年以上が経ち、 国際協力や教育の現場でそ
の取り組みはますます広がっています。
本研究集会は、開発教育の取り組みをより多くの方と共有し、広げていくことと、関連分
野とも連携しながら、その取り組みを深めていくことの2つを目指しています。
特に30回目となる今回は、これまでの開発教育の実践をふまえ、これからの開発教育の方
向性を見出せるような意見交換をめざします。
昨年の東日本大震災後、国内における開発や教育を取り巻く状況は、それまでと大きく変
わりました。 こうした状況で、これからの社会形成にとって開発教育が果たすべき役割
は何か、またそれぞれの実践者は何ができるのか、 参加者の経験交流・意見交換を中心
に据えながら、個別のテーマにそって話し合います。
▼日時
2012年8月4日(土) 10:00~18:10(9:30受付開始/18:30~20:00自由参加の懇親会)
2012年8月5日(日) 10:00~16:30(9:30受付開始)
▼会場
JICA地球ひろば(東京都渋谷区広尾4-2-24)
http://www.jica.go.jp/hiroba/about/map.html
東京メトロ日比谷線広尾駅下車(3番出口)徒歩1分
▼参加費
2日参加 8,000円(DEAR会員・学生は6,000円)
1日参加 4,000円(DEAR会員・学生は3,000円)
※フィールドスタディ参加者は、別途1,000円が追加でかかります。
▼対象
教員、学生(教員志望の方には特におすすめ)、NPO/NGO関係者、国際協力・交流関係者のほか、テーマに関心のある方。
▼1日目(4日)のプログラム
9:30- 受付開始
10:00-12:00 ワークショップ体験(6プログラム)
A 開発教育入門講座「パーム油のはなし」をつかって
B ワークショップ版・世界がもし100人の村だったら
C 「援助」する前に考えよう
D 地球の食卓~フードマイレージ
E グローバル・エクスプレス~ロンドン・オリンピック
F エネルギー・ワークショップ
12:00-13:20 昼食・休憩
13:30-14:30 開会式&全体会「開発教育の30年をふりかえる」
15:00-18:10 実践・研究報告(2コマ)&自主ラウンドテーブル(15コマ)
実践・研究報告(40分×2ラウンド)
1.命の木プロジェクト 世界の子どもたちに、まず5才までの命を。
2.大学生の核リテラシーを育むESDの授業実践:インフュージョン・アプローチ
自主ラウンドテーブル(90分×2ラウンド)
1.関東大震災の「震災作文」から学ぶ開発教育
2.「しあわせしわけ」のワークショップ
3.音楽と平和~音楽は戦争や災害に何ができるのか?~
4.カップめんから世界が見える
5.東日本大震災後のESD~持続可能な地域をつくるESDコーディネーター・開発ファシリテーター
6.現場の変化から学ぶ参加型評価手法:Most Significant Change (MSC)
7.大学生が行って、見て、感じた「開発途上国」と国際協力
8.Visible Thinkingワークショップ~本当の豊かさって何?
9.英国のフェアトレード教材から考える~開発教育×フェアトレード
10.「世界がもしも100人の村だったら」から10年
11.日本の主食・お米の自給とTPP問題
12.世界一大きな授業~NGO、教員、高校生からの実践報告~
13.新たな防災環境教育へ~災害・そのときあなたは?
14.世界の「ゲンジツ」~いろんなものさしを子ども達へ~
15.「水」の授業
18:30-20:00 交流会(参加費別途2,000円)
▼2日目(5日)のプログラム
9:30- 受付開始
10:00-16:00 課題別分科会(4コマ)+フィールドスタディ(2つ)
第1分科会 エネルギーの授業をつくろう
第2分科会 震災後の学び~授業づくりの視点と課題
第3分科会 開発教育の過去・現在・未来-DEAR30周年を迎えて
第4分科会 やってみよう、ミュージカル♪
フィールドスタディⅠ 山谷フィールドスタディ(東京都墨田区)※〆切
フィールドスタディⅡ 持続可能な開発と地域のとりくみ(埼玉県小川町)
16:15-16:30 発表会(自由参加)
▼主催
特定非営利活動法人 開発教育協会/DEAR
▼協賛協力
(独)国際協力機構
▼後援
外務省、文部科学省、(財)自治体国際化協会、(特活)国際協力NGOセンター、
(特活)関西NGO協議会 ※一部申請中のものを含む
▼参加申込み・お問い合わせ先:
特定非営利活動法人 開発教育協会(DEAR)
〒112-0002 東京都文京区小石川2-17-41富坂キリスト教センター2号館3階
TEL 03-5844-3630 FAX 03-3818-5940(平日10:00~18:00)
http://www.dear.or.jp/zenken2012/
http://www.facebook.com/zenken2012
※各プログラムは定員に達し次第締切ります。
▼開発教育協会/DEARとは?
南北格差・貧困・環境・紛争など、地球上で起こっている様々な問題は、私たちの生活と
無関係ではありません。開発教育とは、「知り、考え、行動する」という視点で、身近な
ところからその解決に取り組んでいくための教育活動です。DEARは開発教育を推進するた
めに、1982年から活動しているNGOです。
http://www.dear.or.jp/
主催するのは
特定非営利活動法人 開発教育協会/DEAR
東京開催なのがちょっと残念ですが、暑い夏を「学びと出会いの夏」に変えてみませんか?

■第30回「開発教育全国研究集会」参加者募集スタート!
■8月4日(土)・5日(日)にJICA地球ひろば(東京・広尾)で開催
--------------------------------------------------------------------------------
■http://www.dear.or.jp/zenken2012/
■http://www.facebook.com/zenken2012
--------------------------------------------------------------------------------
日本ではじめて開発教育が紹介されてから30年以上が経ち、 国際協力や教育の現場でそ
の取り組みはますます広がっています。
本研究集会は、開発教育の取り組みをより多くの方と共有し、広げていくことと、関連分
野とも連携しながら、その取り組みを深めていくことの2つを目指しています。
特に30回目となる今回は、これまでの開発教育の実践をふまえ、これからの開発教育の方
向性を見出せるような意見交換をめざします。
昨年の東日本大震災後、国内における開発や教育を取り巻く状況は、それまでと大きく変
わりました。 こうした状況で、これからの社会形成にとって開発教育が果たすべき役割
は何か、またそれぞれの実践者は何ができるのか、 参加者の経験交流・意見交換を中心
に据えながら、個別のテーマにそって話し合います。
▼日時
2012年8月4日(土) 10:00~18:10(9:30受付開始/18:30~20:00自由参加の懇親会)
2012年8月5日(日) 10:00~16:30(9:30受付開始)
▼会場
JICA地球ひろば(東京都渋谷区広尾4-2-24)
http://www.jica.go.jp/hiroba/about/map.html
東京メトロ日比谷線広尾駅下車(3番出口)徒歩1分
▼参加費
2日参加 8,000円(DEAR会員・学生は6,000円)
1日参加 4,000円(DEAR会員・学生は3,000円)
※フィールドスタディ参加者は、別途1,000円が追加でかかります。
▼対象
教員、学生(教員志望の方には特におすすめ)、NPO/NGO関係者、国際協力・交流関係者のほか、テーマに関心のある方。
▼1日目(4日)のプログラム
9:30- 受付開始
10:00-12:00 ワークショップ体験(6プログラム)
A 開発教育入門講座「パーム油のはなし」をつかって
B ワークショップ版・世界がもし100人の村だったら
C 「援助」する前に考えよう
D 地球の食卓~フードマイレージ
E グローバル・エクスプレス~ロンドン・オリンピック
F エネルギー・ワークショップ
12:00-13:20 昼食・休憩
13:30-14:30 開会式&全体会「開発教育の30年をふりかえる」
15:00-18:10 実践・研究報告(2コマ)&自主ラウンドテーブル(15コマ)
実践・研究報告(40分×2ラウンド)
1.命の木プロジェクト 世界の子どもたちに、まず5才までの命を。
2.大学生の核リテラシーを育むESDの授業実践:インフュージョン・アプローチ
自主ラウンドテーブル(90分×2ラウンド)
1.関東大震災の「震災作文」から学ぶ開発教育
2.「しあわせしわけ」のワークショップ
3.音楽と平和~音楽は戦争や災害に何ができるのか?~
4.カップめんから世界が見える
5.東日本大震災後のESD~持続可能な地域をつくるESDコーディネーター・開発ファシリテーター
6.現場の変化から学ぶ参加型評価手法:Most Significant Change (MSC)
7.大学生が行って、見て、感じた「開発途上国」と国際協力
8.Visible Thinkingワークショップ~本当の豊かさって何?
9.英国のフェアトレード教材から考える~開発教育×フェアトレード
10.「世界がもしも100人の村だったら」から10年
11.日本の主食・お米の自給とTPP問題
12.世界一大きな授業~NGO、教員、高校生からの実践報告~
13.新たな防災環境教育へ~災害・そのときあなたは?
14.世界の「ゲンジツ」~いろんなものさしを子ども達へ~
15.「水」の授業
18:30-20:00 交流会(参加費別途2,000円)
▼2日目(5日)のプログラム
9:30- 受付開始
10:00-16:00 課題別分科会(4コマ)+フィールドスタディ(2つ)
第1分科会 エネルギーの授業をつくろう
第2分科会 震災後の学び~授業づくりの視点と課題
第3分科会 開発教育の過去・現在・未来-DEAR30周年を迎えて
第4分科会 やってみよう、ミュージカル♪
フィールドスタディⅠ 山谷フィールドスタディ(東京都墨田区)※〆切
フィールドスタディⅡ 持続可能な開発と地域のとりくみ(埼玉県小川町)
16:15-16:30 発表会(自由参加)
▼主催
特定非営利活動法人 開発教育協会/DEAR
▼協賛協力
(独)国際協力機構
▼後援
外務省、文部科学省、(財)自治体国際化協会、(特活)国際協力NGOセンター、
(特活)関西NGO協議会 ※一部申請中のものを含む
▼参加申込み・お問い合わせ先:
特定非営利活動法人 開発教育協会(DEAR)
〒112-0002 東京都文京区小石川2-17-41富坂キリスト教センター2号館3階
TEL 03-5844-3630 FAX 03-3818-5940(平日10:00~18:00)
http://www.dear.or.jp/zenken2012/
http://www.facebook.com/zenken2012
※各プログラムは定員に達し次第締切ります。
▼開発教育協会/DEARとは?
南北格差・貧困・環境・紛争など、地球上で起こっている様々な問題は、私たちの生活と
無関係ではありません。開発教育とは、「知り、考え、行動する」という視点で、身近な
ところからその解決に取り組んでいくための教育活動です。DEARは開発教育を推進するた
めに、1982年から活動しているNGOです。
http://www.dear.or.jp/
2012年06月29日
世界子供白書2012
 世界子供白書2012
世界子供白書2012サブタイトルは「都市に生きる子どもたち」
世界人口の半分以上が都市や町で暮らしています。10億人以上の子どもたちもその中に含まれます。都市や町で暮らしているからと言って、電気、清潔な水、保健ケアなど健全な生活空間を享受できているとは限りません。学校にも通えず、労働を強いられながら都市や町で暮らしている子どもたちがまだまだたくさんいるのです。
世界子供白書2012には、以下のような5つの行動目標が掲げられています。
・都市部の子どもたちに影響を与えている貧困と排除の規模の大きさとその性質への理解を深める
・インクルージョン(誰もが受け入れられる社会)を阻むものを特定し、取り除く
・都市計画、インフラ開発、サービスの提供、貧困と格差を軽減するための広範な取り組みが、子どもたち特有のニーズと優先事項にしっかりと合うようにする
・都市の貧困層、特に子ども・若者と政府のあらゆるレベルでのパートナーシップを促進する
・社会から取り残され、困窮した子どもたちが自らの権利を十分に享受できるよう、国際社会、国内、地方自治体、コミュニティで支援に取り組む関係者が、様々な資源とエネルギーを出し合う
子供白書ですから、子どものための行動目標です。でも、この5つの目標は、先進国・開発途上国を問わず、現代社会のどこにでもあてはまるように感じます。ますます進む都市化の波は、便利で快適な暮らしと引き換えに、多くの問題を生み出しています。まず、自分自身に置き換えてこれらを考えてみる必要があるのではないでしょうか?『資源とエネルギー』の中には、人間の叡智も含まれているはずです。社会全体がどんな方向に、どのように進み、私たちが個人として、また国として、人間としていかに生きるべきかが問われているような気がします。
白書は読み物としてもとても興味深い内容です。ぜひ、読んでみてください。
ユニセフのHPからダウンロードできますよ

http://www.unicef.or.jp/library/library_wdb.html
2012年06月19日
開発教育を考える⑮
毎週土曜、午後6時10分からNHK総合テレビで『海外ネットワーク』という番組が放送されています。
6月9日は開発教育についてとても考えさせられる特集が組まれていました。
1つ目は「アフリカの飢餓を救え 食糧支援最前線」。
ニジェールなど西アフリカの8か国では、干ばつで1000万人以上が食糧危機に陥っているとのこと。働く場が少なく、現金収入を得ること自体難しい状況に加え、干ばつの影響で、穀物相場が高騰、せっかく現金を手に入れても十分な量の食糧を確保できない現実がレポートされていました。十分な栄養が取れずやせ細った子ども、草をすりつぶしておかゆ様にしたものを食べる人々、からからに乾いた大地。どうしてこんなことに…と考えずにはいられません。レッドカップキャンペーンなどを展開している国連のWFP(世界食糧計画)の現地での支援の様子が取り上げられていました。
同じようにどうしてこんなことが…と思うもう1つのテーマが「児童労働」です。
現在、学校にも行けず労働を強いられている子供は世界に2億人以上いるのです。世界の子ども7人に1人の割合に当たります。人身売買や売春なども後を絶たないようです。以前お伝えしたことがありますが、『子どもの権利条約』の中の『育つ権利』とは、まさに子どもが『教育を受ける』権利です。子どもが学校に通い、学び、自分の未来を自分で切り開く権利です。貧しさのためにその権利が脅かされています。いつか‘権利’などという言葉を使わずに、世界の子どもがみんな教育を受けられる日が来ることを心から願います。
開発教育では飢餓や児童労働について、まず知ることから始まります。現状を知り、その原因を学び、自分たちにできることは何なのかを考えます。
多くの人に情報を伝えることは、募金や支援と同様に大切な活動だと考えます。
だから開発教育はとても身近な教育分野なのです。学びの場は暮らしのそこここにあると信じています
NKH海外ネットワークのHPから、放送分のレポートを読むことができます。
ご紹介します。http://www.nhk.or.jp/worldnet/archives/
6月9日は開発教育についてとても考えさせられる特集が組まれていました。
1つ目は「アフリカの飢餓を救え 食糧支援最前線」。
ニジェールなど西アフリカの8か国では、干ばつで1000万人以上が食糧危機に陥っているとのこと。働く場が少なく、現金収入を得ること自体難しい状況に加え、干ばつの影響で、穀物相場が高騰、せっかく現金を手に入れても十分な量の食糧を確保できない現実がレポートされていました。十分な栄養が取れずやせ細った子ども、草をすりつぶしておかゆ様にしたものを食べる人々、からからに乾いた大地。どうしてこんなことに…と考えずにはいられません。レッドカップキャンペーンなどを展開している国連のWFP(世界食糧計画)の現地での支援の様子が取り上げられていました。
同じようにどうしてこんなことが…と思うもう1つのテーマが「児童労働」です。
現在、学校にも行けず労働を強いられている子供は世界に2億人以上いるのです。世界の子ども7人に1人の割合に当たります。人身売買や売春なども後を絶たないようです。以前お伝えしたことがありますが、『子どもの権利条約』の中の『育つ権利』とは、まさに子どもが『教育を受ける』権利です。子どもが学校に通い、学び、自分の未来を自分で切り開く権利です。貧しさのためにその権利が脅かされています。いつか‘権利’などという言葉を使わずに、世界の子どもがみんな教育を受けられる日が来ることを心から願います。
開発教育では飢餓や児童労働について、まず知ることから始まります。現状を知り、その原因を学び、自分たちにできることは何なのかを考えます。
多くの人に情報を伝えることは、募金や支援と同様に大切な活動だと考えます。
だから開発教育はとても身近な教育分野なのです。学びの場は暮らしのそこここにあると信じています

NKH海外ネットワークのHPから、放送分のレポートを読むことができます。
ご紹介します。http://www.nhk.or.jp/worldnet/archives/
2012年06月10日
開発教育を考える⑭
世界の現状を知るうえで、書物は身近で手ごろな情報ツールですよね。
気軽に読める本として、黒柳徹子さんのエッセイなどいかがでしょうか?
黒柳さんはユニセフの親善大使としてアフリカをはじめたくさんの国を訪れています。
その時の様子や彼女が感じたことをまとめたものが文庫として何冊も出ています。
ちなみに黒柳さんは国連のユニセフ(UNICEF 国連児童基金)から任命されたユニセフの親善大使です。故オードリー・ヘプバーンがユニセフ親善大使として、とても熱心に活動していたことはご存じの方も多いかと思います。ほかにも、ジャッキー・チェン氏やサッカーのベッカム選手、テニスのフェデラー選手なども任命されています。日本人で、国連から任命された親善大使は黒柳さんだけです。
日本には、日本でのユニセフの活動を支援する日本ユニセフ協会というユニセフの国内委員会があります。(ユニセフと日本ユニセフ協会の違いの説明はちょっとややこしいので今回は省きますが、この2つは別組織です。)その日本ユニセフ協会の親善大使を務めているのは、アグネス・チャンさんと日野原重明先生です。
ユニセフ親善大使として訪れた開発途上国の様子をつづった黒柳さんの本は、「開発教育を学ぼう」などと肩肘張らなくても十分楽しく読めますし、感じるところもたくさんあります。
まだ読んだことのない方は一度書店で手に取ってみてください。ちょっとだけ世界が広がりますよ、きっと・・・
気軽に読める本として、黒柳徹子さんのエッセイなどいかがでしょうか?
黒柳さんはユニセフの親善大使としてアフリカをはじめたくさんの国を訪れています。
その時の様子や彼女が感じたことをまとめたものが文庫として何冊も出ています。
ちなみに黒柳さんは国連のユニセフ(UNICEF 国連児童基金)から任命されたユニセフの親善大使です。故オードリー・ヘプバーンがユニセフ親善大使として、とても熱心に活動していたことはご存じの方も多いかと思います。ほかにも、ジャッキー・チェン氏やサッカーのベッカム選手、テニスのフェデラー選手なども任命されています。日本人で、国連から任命された親善大使は黒柳さんだけです。
日本には、日本でのユニセフの活動を支援する日本ユニセフ協会というユニセフの国内委員会があります。(ユニセフと日本ユニセフ協会の違いの説明はちょっとややこしいので今回は省きますが、この2つは別組織です。)その日本ユニセフ協会の親善大使を務めているのは、アグネス・チャンさんと日野原重明先生です。
ユニセフ親善大使として訪れた開発途上国の様子をつづった黒柳さんの本は、「開発教育を学ぼう」などと肩肘張らなくても十分楽しく読めますし、感じるところもたくさんあります。
まだ読んだことのない方は一度書店で手に取ってみてください。ちょっとだけ世界が広がりますよ、きっと・・・

2012年05月24日
開発教育を考える⑬
ベース オブ ピラミッド=Base of the pyramid(BOP)
所得別に人口を積み上げると、下から低所得者層、中間層、富裕層とちょうどピラミッドのように積みあがることから、この低所得者層を指してBOP(ベース オブ ピラミッド)と呼びます。国際金融公社(IFC)と世界資源研究所(WRI)は2007年に、年間所得が3000US$未満をBOPと定義しました。この定義でいくと、BOP層の人口は約40億になります。購買力から考えた市場規模は約5兆ドルで日本1国にも相当します。それだけ経済的にも見込みのある市場、ということでBOPビジネスが脚光を浴びているのです。
世界的に有名なBOPビジネスの取り組みはユニリーバのBOPアプローチです。
プロジェクト・シャクティ(インドなど)
インドでは、衛生的な生活習慣や環境がないために、多くの子どもたちが下痢や肺炎にかかって命を失っています。石鹸を使った手洗いは、子どもたちの命を守る簡単で効果的な方法のひとつです。しかし、インドの農村部には1日2ドル以下の収入で暮らしている方が多く、都市部と同じ価格の石鹸は買っていただくことができません。また、店舗がないため、石鹸を売る手段もありませんでした。
そこで、ユニリーバでは、石鹸を「サシェ」と呼ばれる小分けパックにすることで、単価を1ルピー(約2.5円)と、お求めやすい価格にしました。そして、農村部の女性たちに会計などの知識やスキルを身につけて個人事業主になっていただき、サシェ製品を訪問販売していただいています。2010年までに4万5,000人以上の女性が個人事業主になり、10万の村で300万世帯にユニリーバの製品を届けています。現在、バングラデシュ、スリランカ、ベトナムにも取り組みを広げ、2015年までに女性人事業主を7万5,000人に増やすことをめざしています。
このプロジェクトは、石鹸の普及によるコミュニティの衛生状態の改善、女性たちの経済的・精神的自立、ユニリーバのビジネスの成長という3つの目的を同時に満たした、BOP(ベース・オブ・ピラミッド)ビジネスの先進的な事例として、国際的にも高い評価を受けています。(ユニリーバ・ジャパンのHPより抜粋)
BOPビジネスが是か非か、判断は難しいところだと思います。ただ、BOPビジネスの場合、企業だけでなく開発援助機関やNGO団体などが提携して事業にあたることが多いようです。今まで、貧困ゆえに経済活動の枠組みの外側に取り残されていた人々が、職を得、またものを買うことができるようになるということは、貧困から生まれる格差を解消するための1つの手段となりうるのではないかと考えます。フェアトレードが開発途上国から世界に向けての経済活動の発信だとすれば、BOPビジネスは先進国や先進企業から開発途上国への働きかけといえるのかも知れません。ただ、こうした流れによって低所得者層といわれる人たちが、さらに搾取されることのないよう願っています。
BOPについては日本ではまだまだ周知不足、勉強不足の感があります。開発教育の分野でも、BOPという言葉を手掛かりに格差について考えていけたらいいなと思っています。キーワードから世界を考える、という取り組みもまた1つの国際理解だと思います
所得別に人口を積み上げると、下から低所得者層、中間層、富裕層とちょうどピラミッドのように積みあがることから、この低所得者層を指してBOP(ベース オブ ピラミッド)と呼びます。国際金融公社(IFC)と世界資源研究所(WRI)は2007年に、年間所得が3000US$未満をBOPと定義しました。この定義でいくと、BOP層の人口は約40億になります。購買力から考えた市場規模は約5兆ドルで日本1国にも相当します。それだけ経済的にも見込みのある市場、ということでBOPビジネスが脚光を浴びているのです。
世界的に有名なBOPビジネスの取り組みはユニリーバのBOPアプローチです。
プロジェクト・シャクティ(インドなど)
インドでは、衛生的な生活習慣や環境がないために、多くの子どもたちが下痢や肺炎にかかって命を失っています。石鹸を使った手洗いは、子どもたちの命を守る簡単で効果的な方法のひとつです。しかし、インドの農村部には1日2ドル以下の収入で暮らしている方が多く、都市部と同じ価格の石鹸は買っていただくことができません。また、店舗がないため、石鹸を売る手段もありませんでした。
そこで、ユニリーバでは、石鹸を「サシェ」と呼ばれる小分けパックにすることで、単価を1ルピー(約2.5円)と、お求めやすい価格にしました。そして、農村部の女性たちに会計などの知識やスキルを身につけて個人事業主になっていただき、サシェ製品を訪問販売していただいています。2010年までに4万5,000人以上の女性が個人事業主になり、10万の村で300万世帯にユニリーバの製品を届けています。現在、バングラデシュ、スリランカ、ベトナムにも取り組みを広げ、2015年までに女性人事業主を7万5,000人に増やすことをめざしています。
このプロジェクトは、石鹸の普及によるコミュニティの衛生状態の改善、女性たちの経済的・精神的自立、ユニリーバのビジネスの成長という3つの目的を同時に満たした、BOP(ベース・オブ・ピラミッド)ビジネスの先進的な事例として、国際的にも高い評価を受けています。(ユニリーバ・ジャパンのHPより抜粋)
BOPビジネスが是か非か、判断は難しいところだと思います。ただ、BOPビジネスの場合、企業だけでなく開発援助機関やNGO団体などが提携して事業にあたることが多いようです。今まで、貧困ゆえに経済活動の枠組みの外側に取り残されていた人々が、職を得、またものを買うことができるようになるということは、貧困から生まれる格差を解消するための1つの手段となりうるのではないかと考えます。フェアトレードが開発途上国から世界に向けての経済活動の発信だとすれば、BOPビジネスは先進国や先進企業から開発途上国への働きかけといえるのかも知れません。ただ、こうした流れによって低所得者層といわれる人たちが、さらに搾取されることのないよう願っています。
BOPについては日本ではまだまだ周知不足、勉強不足の感があります。開発教育の分野でも、BOPという言葉を手掛かりに格差について考えていけたらいいなと思っています。キーワードから世界を考える、という取り組みもまた1つの国際理解だと思います

2012年05月05日
子どもの権利条約
5月5日は子どもの日。日本では15歳未満の子どもの数が31年連続で減少しているとの総務省の発表がありました。日本の人口に占める子どもの割合は、世界のそれと比べると2分の1、逆にお年寄りの割合は2倍になっています。少子高齢化が進んでいるということですね。
子どもの日を迎え、5日付の静岡新聞の社説に「子どもの権利条約」のことが述べられています。「子どもの権利条約」については、以前ワクらぼのブログでも取り上げましたのでお読みいただいているかも…
まだの方はこちらから→http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e844832.html
『 子どもの権利条約は18歳未満の子どもの基本的人権を国際的に保障する条約。
89年の第44回国連総会で採択され、90年に発効した。
健康に生まれ、十分な栄養を得て元気に成長する「生きる」、差別、虐待などから
「守られる」、教育などを受ける「育つ」、自由に意見を言ったり、グループで活動
したりできる「参加する」各権利を定めている。この中には国籍を持つ権利も盛り
込まれた。』(静岡新聞・5月5日付朝刊3面社説より引用)
経済的に貧しく十分な栄養をとれず、また学校に通うことのできない世界の子どもたちには是非ともこの権利が行使できる日を望みます。
日本でも‘子どもの権利’はしっかりと守られるべきです。虐待を受けたり、震災の影響で不自由な暮らしを強いられている子どもたちがまだまだいることを考えていかなければならないと、そんなことを思った子どもの日でした
子どもの日を迎え、5日付の静岡新聞の社説に「子どもの権利条約」のことが述べられています。「子どもの権利条約」については、以前ワクらぼのブログでも取り上げましたのでお読みいただいているかも…
まだの方はこちらから→http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e844832.html
『 子どもの権利条約は18歳未満の子どもの基本的人権を国際的に保障する条約。
89年の第44回国連総会で採択され、90年に発効した。
健康に生まれ、十分な栄養を得て元気に成長する「生きる」、差別、虐待などから
「守られる」、教育などを受ける「育つ」、自由に意見を言ったり、グループで活動
したりできる「参加する」各権利を定めている。この中には国籍を持つ権利も盛り
込まれた。』(静岡新聞・5月5日付朝刊3面社説より引用)
経済的に貧しく十分な栄養をとれず、また学校に通うことのできない世界の子どもたちには是非ともこの権利が行使できる日を望みます。
日本でも‘子どもの権利’はしっかりと守られるべきです。虐待を受けたり、震災の影響で不自由な暮らしを強いられている子どもたちがまだまだいることを考えていかなければならないと、そんなことを思った子どもの日でした

2012年05月03日
ハンガーマップ
 ハンガーマップを見たことありますか?
ハンガーマップを見たことありますか?←クリックしてじっくり見てください!
ハンガーマップは、世界の飢餓の状況を地図に色分けしたものです。栄養不足の人がどのくらいいるのかを人口の割合で5段階に分けて表しています。飢餓人口の割合が高いところが赤色で塗られています。赤色で塗られた国では全人口の35%以上が栄養不足の状態にあります。ハンガーマップは、国連世界食糧計画(WFP)が国連食糧農業機関(FAO)の統計に基づき作成しています。
では、そもそも飢餓とは…
飢餓とは、身長に対して妥当とされる最低限の体重を維持し、軽度の活動を行うのに必要なエネルギー(カロリー数)を摂取できていない状態を指します。必要なカロリー数は、年齢や性別、体の大きさ、活動量等によって変わります。(~WFP HPより引用~)
現在世界では、9億2500万人が飢餓に苦しんでいます。世界の総人口から考えると7人に1人の割合になります。その75%は開発途上国の農村部に暮らす人々です。子どもの成長には栄養が欠かせません。開発途上国で子どもが命を落とす原因の3分の1は栄養失調が原因だと言われています。
食は文化であるとともに、人間が生きていく上でなくてはならないものです。飽食といわれる現代、私たちはもっと「食べる」ことを考えなければならないのだと思います。食は楽しむものであり、また命をつなぐものでもあるのですね。
そんなことを思いながら、いろいろな角度から‘食’をとらえ、考えていけたらよいなと思っています