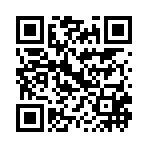2012年07月20日
開発教育を考える⑭
「難民」という言葉を一度は聞いたことがありますよね。
「難民」は、1951年に国連で採択された『難民の地位に関する条約』で以下のように定義づけられています。
「人権、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受ける恐れがあるために他国に逃れた」人々。
これに対して、自国を出ずに、自国の中で避難生活を強いられている人々を「国内避難民」といいます。「難民」と「国内避難民」とは、正式には使い分けがされています。メディア等の報道で「難民」といわれる場合、彼らは国外に避難した人々です。
紛争や内戦、自然災害などで、とるものもとりあえず命からがら逃れるため、人々は何日もかけて歩いて国境を越え自国から隣国へと移動することが多いです。難民たちを収容するために難民キャンプと呼ばれるものが作られます。逃れてきた難民を保護、収容する施設です。一斉に多くの人々が避難してきた場合、それを受け入れる側にも限界があります。国連を初め、様々な機関やNGOなどが援助の手を差しのべますが、施設の環境は厳しいものです。そしてその厳しい環境で多く犠牲になるのは、弱いもの(子どもやお年寄り)です。
“国境なき医師団”が作成した『難民キャンプへ』(Virtual Tour of a Refugee Camp)をご紹介します。http://www.msf.or.jp/com/camp/index.html
シリアの国内情勢が厳しさを増しています。たくさんの難民が隣国レバノンに逃れているというニュースが流れています。このような現実に目を向け、今世界でどのようなことが起こっているのかを知ること・考えることは、開発教育ではとても大切なことだと思います。知ること・考えることで何が変わるのか? 何も変わらないかもしれない…と思いつつ、でもやはり知ることは重要だと思うのです。そこに開発教育の意義があるのではと願いつつ、開発教育に取り組みたいと考えています
「難民」は、1951年に国連で採択された『難民の地位に関する条約』で以下のように定義づけられています。
「人権、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受ける恐れがあるために他国に逃れた」人々。
これに対して、自国を出ずに、自国の中で避難生活を強いられている人々を「国内避難民」といいます。「難民」と「国内避難民」とは、正式には使い分けがされています。メディア等の報道で「難民」といわれる場合、彼らは国外に避難した人々です。
紛争や内戦、自然災害などで、とるものもとりあえず命からがら逃れるため、人々は何日もかけて歩いて国境を越え自国から隣国へと移動することが多いです。難民たちを収容するために難民キャンプと呼ばれるものが作られます。逃れてきた難民を保護、収容する施設です。一斉に多くの人々が避難してきた場合、それを受け入れる側にも限界があります。国連を初め、様々な機関やNGOなどが援助の手を差しのべますが、施設の環境は厳しいものです。そしてその厳しい環境で多く犠牲になるのは、弱いもの(子どもやお年寄り)です。
“国境なき医師団”が作成した『難民キャンプへ』(Virtual Tour of a Refugee Camp)をご紹介します。http://www.msf.or.jp/com/camp/index.html
シリアの国内情勢が厳しさを増しています。たくさんの難民が隣国レバノンに逃れているというニュースが流れています。このような現実に目を向け、今世界でどのようなことが起こっているのかを知ること・考えることは、開発教育ではとても大切なことだと思います。知ること・考えることで何が変わるのか? 何も変わらないかもしれない…と思いつつ、でもやはり知ることは重要だと思うのです。そこに開発教育の意義があるのではと願いつつ、開発教育に取り組みたいと考えています

Posted byワクらぼat20:17
Comments(0)
開発教育を考える