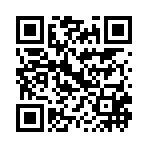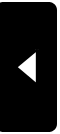2012年04月27日
開発教育を考える⑫
最近よく使われる言葉に「持続可能な~」という表現があります。英語のsustainable(サステイナブル)を日本語にした言い方です。sustainableという英語が国連の環境問題の分野で使われたことで広く世間で認知されるようになり、日本でも近年いろいろなところでこの表現が使われています。「持続可能な社会」「持続可能なエネルギー」「持続可能な開発」など…
開発教育の世界でも『持続可能な開発のための教育』(Education for Sustainable Development 通称ESD)という活動が行われています。ESDとはどんな活動なのでしょう?
ESDとは、社会の課題と身近な暮らしを結びつけ、新たな価値観や行動を生み出すことを目指す学習や活動です。
例えば、持続不可能な社会の課題を知り、その原因と向き合う。それらを解決するためにできることを考え、実際に行動する。そのような経験を通じて、社会の一員としての認識や行動力が育まれていきます。
また、豊かな自然といのちのつながりを感じたり、地域に根ざした伝統文化や人びとと触れながら、人と自然、人と人との共存や多様な生き方を学ぶといったことも、ESDのアプローチのひとつです。(認定NPO法人「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議(ESD-J)HPより引用)
国連や多くの国で取り入れられており、先日、ワクらぼ が参加した『世界中の子どもに教育を』というキャンペーンも世界規模で行われているESD活動の1つです。
市民やNGO・NPO、民間団体が地域で自主的に行っているものもたくさんあります。ワクらぼ の開催しているワークショップのいくつかは小さなESD活動だと考えています。
とはいえ、どんなことが、どんな方法が「持続可能」なことなのか? 逆に「持続不可能」とはどんな状態なのか? ちょっとわかりにくいですよね。言葉だけが流行りのように空回りしてしまうのも残念です。だから、いろんな手法にチャレンジしていこうと思います。
地球に住む、今を生きる私たちが、そして未来を作る子どもたちが、笑顔で健やかに、幸せに生きることのできる社会が「持続可能な」社会なのでしょう。難しい課題です。みんなでそのあるべき姿を考えていくことが大切なのだと思います
開発教育の世界でも『持続可能な開発のための教育』(Education for Sustainable Development 通称ESD)という活動が行われています。ESDとはどんな活動なのでしょう?
ESDとは、社会の課題と身近な暮らしを結びつけ、新たな価値観や行動を生み出すことを目指す学習や活動です。
例えば、持続不可能な社会の課題を知り、その原因と向き合う。それらを解決するためにできることを考え、実際に行動する。そのような経験を通じて、社会の一員としての認識や行動力が育まれていきます。
また、豊かな自然といのちのつながりを感じたり、地域に根ざした伝統文化や人びとと触れながら、人と自然、人と人との共存や多様な生き方を学ぶといったことも、ESDのアプローチのひとつです。(認定NPO法人「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議(ESD-J)HPより引用)
国連や多くの国で取り入れられており、先日、ワクらぼ が参加した『世界中の子どもに教育を』というキャンペーンも世界規模で行われているESD活動の1つです。
市民やNGO・NPO、民間団体が地域で自主的に行っているものもたくさんあります。ワクらぼ の開催しているワークショップのいくつかは小さなESD活動だと考えています。
とはいえ、どんなことが、どんな方法が「持続可能」なことなのか? 逆に「持続不可能」とはどんな状態なのか? ちょっとわかりにくいですよね。言葉だけが流行りのように空回りしてしまうのも残念です。だから、いろんな手法にチャレンジしていこうと思います。
地球に住む、今を生きる私たちが、そして未来を作る子どもたちが、笑顔で健やかに、幸せに生きることのできる社会が「持続可能な」社会なのでしょう。難しい課題です。みんなでそのあるべき姿を考えていくことが大切なのだと思います

2012年04月08日
開発教育を考える⑪
読み書きができない、とはどういう状態なのか?識字率がほぼ100%の日本では考えられない現実です。
読み書きができないと、安定した職業に就けません。職業が安定しないと収入が少なくなります。収入が僅かだと子どもまで家の手伝いや労働をしなければなりません。そんな状況では子どもを学校に通わせることはできません。学校に行けないということは教育を受けられないということですから、子どもたちは読み書きができません。読み書きを学ばずに大人になってしまいますから、仕事は限られます。安定した職業には就けません。職業が安定しないと収入が少なくなります。収入が僅かだと・・・というようにずっと貧しいまま、そこから抜け出せなくなります。これを‘貧困のサイクル’と呼びます。
読み書きや計算ができないということは、自分の名前も書けないということです。仕事のマニュアルが読めません。仕事の書類が書けません。雇用契約を結ぶにしても契約書面に書いてあることがわかりませんから、自分がどんな条件で働くことになるかがわかりません。一生懸命働いても手にした賃金が正当なものであるのかの判断ができません。とても深刻な問題です。最低限の読み書きと簡単な計算ができれば、劣悪な条件での雇用を受け入れる必要が減り、また肉体労働以外にも働くすべが生まれます。だから、子どもたちは学校に通い、読み書きと簡単な計算を学ぶ必要があるのです。生まれた場所によって、学校に通い学ぶ権利に格差ができてはならないはずです。でも世界には、貧困のサイクルから抜け出せず、学校に通うことができずに働いている子供たちがまだたくさんいます。
どうしたら一人でも多くの子供たちが学校に通い、文字や計算を学び、自分の未来を自分で考える(決める)ことができるようになるのかを考えていくべきだと思います。開発教育はそういう現実を多くの人たちに伝えていく学びの場です。
この‘貧困のサイクル’のことは、日本ユネスコ協会連盟のHP『世界寺子屋運動』にわかりやすく掲載されています。http://www.unesco.or.jp/terakoya/ ぜひ、ご覧ください
読み書きができないと、安定した職業に就けません。職業が安定しないと収入が少なくなります。収入が僅かだと子どもまで家の手伝いや労働をしなければなりません。そんな状況では子どもを学校に通わせることはできません。学校に行けないということは教育を受けられないということですから、子どもたちは読み書きができません。読み書きを学ばずに大人になってしまいますから、仕事は限られます。安定した職業には就けません。職業が安定しないと収入が少なくなります。収入が僅かだと・・・というようにずっと貧しいまま、そこから抜け出せなくなります。これを‘貧困のサイクル’と呼びます。
読み書きや計算ができないということは、自分の名前も書けないということです。仕事のマニュアルが読めません。仕事の書類が書けません。雇用契約を結ぶにしても契約書面に書いてあることがわかりませんから、自分がどんな条件で働くことになるかがわかりません。一生懸命働いても手にした賃金が正当なものであるのかの判断ができません。とても深刻な問題です。最低限の読み書きと簡単な計算ができれば、劣悪な条件での雇用を受け入れる必要が減り、また肉体労働以外にも働くすべが生まれます。だから、子どもたちは学校に通い、読み書きと簡単な計算を学ぶ必要があるのです。生まれた場所によって、学校に通い学ぶ権利に格差ができてはならないはずです。でも世界には、貧困のサイクルから抜け出せず、学校に通うことができずに働いている子供たちがまだたくさんいます。
どうしたら一人でも多くの子供たちが学校に通い、文字や計算を学び、自分の未来を自分で考える(決める)ことができるようになるのかを考えていくべきだと思います。開発教育はそういう現実を多くの人たちに伝えていく学びの場です。
この‘貧困のサイクル’のことは、日本ユネスコ協会連盟のHP『世界寺子屋運動』にわかりやすく掲載されています。http://www.unesco.or.jp/terakoya/ ぜひ、ご覧ください

2012年04月03日
『地球のステージ』について
『地球のステージ』公演を知っていますか?
NPO法人地球のステージが行っているコンサート形式のステージです。戦争や貧困の中でも笑顔を忘れず、明るく元気にそして強く生きる子供たちの姿を、オリジナルの音楽と映像、語りで伝えてくれます。(詳しくはhttp://e-stageone.org/まで)
とても素晴らしいステージです。
ステージは1から5まで、そして東日本大震災を受けて災害特別編もあります。どれも心に残ります。草の根的な活動で、全国にたくさんのファンがいるはず!静岡にもいますよね?!
6月に磐田国際交流協会主催でコンサートがあるようです。
静岡市でもぜひ『地球のステージ』公演を開催したいと考えています。近い将来その夢がかなうようがんばって活動していきます
NPO法人地球のステージが行っているコンサート形式のステージです。戦争や貧困の中でも笑顔を忘れず、明るく元気にそして強く生きる子供たちの姿を、オリジナルの音楽と映像、語りで伝えてくれます。(詳しくはhttp://e-stageone.org/まで)
とても素晴らしいステージです。
ステージは1から5まで、そして東日本大震災を受けて災害特別編もあります。どれも心に残ります。草の根的な活動で、全国にたくさんのファンがいるはず!静岡にもいますよね?!
6月に磐田国際交流協会主催でコンサートがあるようです。
静岡市でもぜひ『地球のステージ』公演を開催したいと考えています。近い将来その夢がかなうようがんばって活動していきます

2012年04月01日
開発教育『教材体験フェスタ』
先月24日、25日に東京・広尾のJICA地球ひろばで開催された(特活)開発教育協会DEARの『教材体験フェスタ』が盛況のうちに終了したとのこと。その時の模様がHPにアップされました。
皆さんのワークショップの様子をぜひご覧ください。感想も掲載されています。http://www.dear.or.jp/festa2012/report_1.html
4月21日に ワクらぼ で企画している「世界がもし100人の村だったら」の感想も載っていますよ。
いつか近い将来、静岡でもこんな体験フェアができたらいいなあと常々考えています。開発教育に興味のある方、ゲームやアクティビティでワークショップを楽しみたい方、子どもたちに楽しみながら世界や社会のことを教えたい先生方、・・・ぜひ一緒に企画していきませんか?
皆さんのワークショップの様子をぜひご覧ください。感想も掲載されています。http://www.dear.or.jp/festa2012/report_1.html
4月21日に ワクらぼ で企画している「世界がもし100人の村だったら」の感想も載っていますよ。
いつか近い将来、静岡でもこんな体験フェアができたらいいなあと常々考えています。開発教育に興味のある方、ゲームやアクティビティでワークショップを楽しみたい方、子どもたちに楽しみながら世界や社会のことを教えたい先生方、・・・ぜひ一緒に企画していきませんか?
2012年03月28日
水を考える
地球上には14億k㎥の水があるそうです。どのくらいの量なのか想像がつきませんが…
では、ここで問題です。この途方もない量の水のうち、海水はどのくらいを占めるのでしょうか?
答えは約97%。つまり、地球上の水のほとんどが塩分を含んでいるということになります。残り3%弱が淡水となりますが、その多くは北極、南極地域の氷だそうです。私たち人間が使うことのできる地下水、河川、湖沼にある淡水の量は、地球上の水の総量の僅か0.8%に過ぎません。そのほとんどが地下水なので、実際私たちが容易に手に入れることのできる川や湖の水はさらに少なくなって、総量の0.01%しかないそうです。0.01%の水でも人間の住むところに均一に供給されていれば、人間が生活するのに十分な量だというからそれもまたちょっと驚きです。本当に地球は「水の惑星」なのですね。
2012年3月6日に発表されたユニセフとWHO(世界保健機関)の合同報告書によると、国連のミレニアム開発目標(MDGs)の1つ、「安全な飲料水を利用できない人々の割合を半減する」という目標が、目標達成期限の2015年より早く達成されました。2010年末には世界の人口の89%が改善された水源を利用しています。2015年には92%になる見通しです。
しかし、世界では毎日3000人以上の子どもたちが下痢性疾患によって命を落としているという現実があります。不衛生な水を飲むことによりお腹を壊し、下痢による脱水症状で命を落とすのです。子どもを含め7億8000万人の人々がまだ安全な水を得られていないのです。残念ながら地球の豊かな水の恵みは、公平に私たちに与えられていません。
日本では蛇口をひねれば水が出ます。しかも水道水は日本中ほぼどこでもそのまま飲むことができます。水道水を飲んでおなかを壊すことはありません。
日本に暮らしていると忘れがちな水の大切さを、いろいろな数字から考えてみるのも大事なことではないでしょうか?
では、ここで問題です。この途方もない量の水のうち、海水はどのくらいを占めるのでしょうか?
答えは約97%。つまり、地球上の水のほとんどが塩分を含んでいるということになります。残り3%弱が淡水となりますが、その多くは北極、南極地域の氷だそうです。私たち人間が使うことのできる地下水、河川、湖沼にある淡水の量は、地球上の水の総量の僅か0.8%に過ぎません。そのほとんどが地下水なので、実際私たちが容易に手に入れることのできる川や湖の水はさらに少なくなって、総量の0.01%しかないそうです。0.01%の水でも人間の住むところに均一に供給されていれば、人間が生活するのに十分な量だというからそれもまたちょっと驚きです。本当に地球は「水の惑星」なのですね。
2012年3月6日に発表されたユニセフとWHO(世界保健機関)の合同報告書によると、国連のミレニアム開発目標(MDGs)の1つ、「安全な飲料水を利用できない人々の割合を半減する」という目標が、目標達成期限の2015年より早く達成されました。2010年末には世界の人口の89%が改善された水源を利用しています。2015年には92%になる見通しです。
しかし、世界では毎日3000人以上の子どもたちが下痢性疾患によって命を落としているという現実があります。不衛生な水を飲むことによりお腹を壊し、下痢による脱水症状で命を落とすのです。子どもを含め7億8000万人の人々がまだ安全な水を得られていないのです。残念ながら地球の豊かな水の恵みは、公平に私たちに与えられていません。
日本では蛇口をひねれば水が出ます。しかも水道水は日本中ほぼどこでもそのまま飲むことができます。水道水を飲んでおなかを壊すことはありません。
日本に暮らしていると忘れがちな水の大切さを、いろいろな数字から考えてみるのも大事なことではないでしょうか?

2012年03月20日
開発教育を考える⑩
以前このテーマで外務省の『キッズ外務省』をご紹介しました。今回はユニセフのHPにある『子どもと先生の広場』をご紹介します。
http://www.unicef.or.jp/kodomo/index.html
ユニセフの組織や活動についての情報を中心に子どもたちにわかりやすく説明しているサイトですが、世界の子どもたちのデータをここから調べることができます。『世界子供白書』もここからダウンロードすることができますよ。開発教育の統計データを調べたい時に役に立ちます。
たとえば、『子どもと先生の広場』の中の、「世界の子どもデータ」に入って、「世界地図で見てみたい」から調べると、地図の上での子どもたちの格差がとてもよくわかります。アフリカでは、小学校に入学できても卒業まで通えない子どもの割合が60%以上の国がほとんどです。つまり10人中6人はせっかく入った小学校を卒業できないのです。そんな情報を私たちはインターネット上で簡単に見ることができるのですね。
なるべく多くの方に見て、知っていただきたいと思います。知るだけでは何にもならない、とおっしゃる方もいるでしょう。でも、‘知ること’は大事なことだと思いませんか?!‘知ること’は‘学ぶこと’であり、‘学ぶこと’は‘考えること’だと思います。そしてそこからいろいろなことが始まっていくのではないかと考えるのです。ぜひ一度のぞいてみてくださいね
http://www.unicef.or.jp/kodomo/index.html
ユニセフの組織や活動についての情報を中心に子どもたちにわかりやすく説明しているサイトですが、世界の子どもたちのデータをここから調べることができます。『世界子供白書』もここからダウンロードすることができますよ。開発教育の統計データを調べたい時に役に立ちます。
たとえば、『子どもと先生の広場』の中の、「世界の子どもデータ」に入って、「世界地図で見てみたい」から調べると、地図の上での子どもたちの格差がとてもよくわかります。アフリカでは、小学校に入学できても卒業まで通えない子どもの割合が60%以上の国がほとんどです。つまり10人中6人はせっかく入った小学校を卒業できないのです。そんな情報を私たちはインターネット上で簡単に見ることができるのですね。
なるべく多くの方に見て、知っていただきたいと思います。知るだけでは何にもならない、とおっしゃる方もいるでしょう。でも、‘知ること’は大事なことだと思いませんか?!‘知ること’は‘学ぶこと’であり、‘学ぶこと’は‘考えること’だと思います。そしてそこからいろいろなことが始まっていくのではないかと考えるのです。ぜひ一度のぞいてみてくださいね

2012年03月12日
開発教育を考える⑨
 国連のミレニアム開発目標(MDGs)は、
国連のミレニアム開発目標(MDGs)は、~2005年・・・初等・中等教育の男女格差解消
~2015年・・・初等教育の完全普及 という目標を掲げました。
確かに、学校に行けない子どもは少しずつ減っています。しかし、2010年現在も6,700万の子どもが学校に通っていません。2015年になっても5,600万人の子どもが学校に通えないことが予想されます。
学校に通えない子どものうち女の子の占める割合は50%を越えます。特にサハラ砂漠以南のアフリカでは1,200万人の女の子が1度も学校に通うことなく一生を終えます。
開発教育では、このような現実を一人でも多くの方に伝えることを目指しています。どうすれば伝わるのか?!工夫が必要になります。NGOやNPO、市民団体、教育機関やユニセフ、ユネスコなど様々な団体が、その特性を生かし広報、教育活動を実施しています。
広報活動の1つとして『世界中の子どもに教育を』という世界的なキャンペーンがあります。2003年に始まり、毎年4月に世界規模で行われます。
世界中の子どもたちが、「なぜ、世界には学校に行けない子どもたちがいるの?」「どうしたらみんなが学校に通えるようになるの?」「今、私たちにできることって?」といった教育に関する問題(開発教育)を、期間を定めて一斉に学びます。これを『世界一大きな授業』と呼んでいます。
日本では、途上国のこども支援を行うNGOからなる教育協力NGOネットワークがこのキャンペーンを実施しています。多くの教職員の方が参加され、小学校から大学までいろいろなところで授業が行われて生徒や学生が開発教育を学びます。昨年の参加校は270校、参加者は35,371名でした。(詳細はhttp://www.jnne.org/gce2012/をご覧ください。)
もちろん大人でも市民団体でもこのキャンペーンに参加できます。ワクらぼ も昨年からこのキャンペーンに参加しています。今年は、4月21日(土)アイセル21で『世界がもし100人の村だったら』のワークショップを開催します。(詳細は後日アップしますね!)
開発教育というちょっと堅苦しく難しそうな言葉が、広くたくさんの人々になじみ、気軽で参加しやすい活動になることを心から願っています

2012年03月04日
開発教育を考える⑧
開発教育とは、世界で起こっている貧困・飢餓・紛争・環境破壊・人権侵害などの問題を取り上げ、その現状を知り、自分の置かれている立場で何ができるのかをみなで考え、行動を起こすきっかけとなる学びの場を作る活動です。
開発教育の統計的指標は国連から出される様々な白書をもとに提供されることがあります。
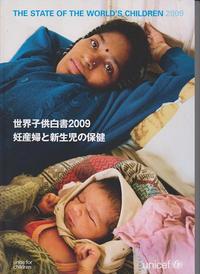 たとえば、世界各国の子どもたちがどんな状況にあるのかを知るにはユニセフ(国連児童基金)が1980年から刊行している『世界子供白書』が参考になります。この白書には世界の貧困国や途上国の子ども、幼児の栄養や教育の状態が数字で統計的にまとめられています。また毎年テーマを決めて、そのテーマに関する詳細な現状分析や活動方針などを論じています。2011年のテーマは『青少年期<10代>可能性に満ちた世代(Adolescence An Age Of Opportunity)』でした。読み応えのある白書に仕上がっています。
たとえば、世界各国の子どもたちがどんな状況にあるのかを知るにはユニセフ(国連児童基金)が1980年から刊行している『世界子供白書』が参考になります。この白書には世界の貧困国や途上国の子ども、幼児の栄養や教育の状態が数字で統計的にまとめられています。また毎年テーマを決めて、そのテーマに関する詳細な現状分析や活動方針などを論じています。2011年のテーマは『青少年期<10代>可能性に満ちた世代(Adolescence An Age Of Opportunity)』でした。読み応えのある白書に仕上がっています。
白書に収められた数字がすべて確実なものかどうかの判断は難しいところです。なぜなら、貧困国の中には国が国家として機能せず、統計を取ることさえ困難なところもあるからです。また多くの国には数字だけではとらえきれない様々な問題が隠されています。ただ、開発教育を学ぶとき、具体的な数字を示されることでその問題がぐっと身近に感じられることも事実です。その意味で、国連をはじめ国や実績のあるNGOなどが発表している資料を活用することはとても大切なことだと考えます。
ワクらぼでは、出来るだけ具体的にわかりやすく、そしてなるべく正確な情報を提供し、世界の現状をお伝えしていけるように努力していきたいと考えております
開発教育の統計的指標は国連から出される様々な白書をもとに提供されることがあります。
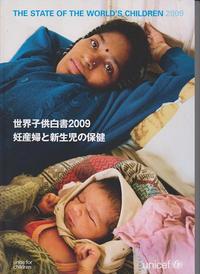 たとえば、世界各国の子どもたちがどんな状況にあるのかを知るにはユニセフ(国連児童基金)が1980年から刊行している『世界子供白書』が参考になります。この白書には世界の貧困国や途上国の子ども、幼児の栄養や教育の状態が数字で統計的にまとめられています。また毎年テーマを決めて、そのテーマに関する詳細な現状分析や活動方針などを論じています。2011年のテーマは『青少年期<10代>可能性に満ちた世代(Adolescence An Age Of Opportunity)』でした。読み応えのある白書に仕上がっています。
たとえば、世界各国の子どもたちがどんな状況にあるのかを知るにはユニセフ(国連児童基金)が1980年から刊行している『世界子供白書』が参考になります。この白書には世界の貧困国や途上国の子ども、幼児の栄養や教育の状態が数字で統計的にまとめられています。また毎年テーマを決めて、そのテーマに関する詳細な現状分析や活動方針などを論じています。2011年のテーマは『青少年期<10代>可能性に満ちた世代(Adolescence An Age Of Opportunity)』でした。読み応えのある白書に仕上がっています。白書に収められた数字がすべて確実なものかどうかの判断は難しいところです。なぜなら、貧困国の中には国が国家として機能せず、統計を取ることさえ困難なところもあるからです。また多くの国には数字だけではとらえきれない様々な問題が隠されています。ただ、開発教育を学ぶとき、具体的な数字を示されることでその問題がぐっと身近に感じられることも事実です。その意味で、国連をはじめ国や実績のあるNGOなどが発表している資料を活用することはとても大切なことだと考えます。
ワクらぼでは、出来るだけ具体的にわかりやすく、そしてなるべく正確な情報を提供し、世界の現状をお伝えしていけるように努力していきたいと考えております

2012年02月19日
開発教育を考える⑦
開発教育のワークショップや講師派遣などを行っている民間組織はNGOと呼ばれることが多いです。日本でも多くのNGOが開発途上国の貧困や教育格差、生活改善などの問題に取り組んでいます。日本発の団体もありますし、海外の団体の日本支部という形をとって国際的な組織で活動しているところもあります。
NGOは英語のNon-Governmental Organizations(非政府組織)の頭文字をとっています。国家に介入されることなく、政府や政治活動を超えて民間で活動するという意味で非政府という言葉が使われます。国連で使用され、広まった言葉だと言われています。
日本では、国際支援や国際協力をする団体をNGO、国内で活動する団体をNPO(Nonprofit-Organization 非営利団体)と捉える傾向があるようです。
新聞やテレビ、書籍などメディアではNGOという言葉が出てくることが結構あります。ちょっとだけ意識して読んだり聞いたりしてみてください。開発教育がほんの少し身近に感じられるかもしれませんよ
NGOは英語のNon-Governmental Organizations(非政府組織)の頭文字をとっています。国家に介入されることなく、政府や政治活動を超えて民間で活動するという意味で非政府という言葉が使われます。国連で使用され、広まった言葉だと言われています。
日本では、国際支援や国際協力をする団体をNGO、国内で活動する団体をNPO(Nonprofit-Organization 非営利団体)と捉える傾向があるようです。
新聞やテレビ、書籍などメディアではNGOという言葉が出てくることが結構あります。ちょっとだけ意識して読んだり聞いたりしてみてください。開発教育がほんの少し身近に感じられるかもしれませんよ

2012年02月14日
開発教育を考える⑥
「子どもの権利条約」って知っていますか?
子どもの基本的人権を保障するために定められた条約です。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本が批准したのは1994年です。
「子どもの権利条約」には4つの柱となる権利があります。
「子どもの権利条約」-4つの柱
☆生きる権利
子どもたちは健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、健やかに成長する権利を持っています。
☆守られる権利
子どもたちは、あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られなければなりません。紛争下の子ども、障害をもつ子ども、少数民族の子どもなどは特別に守られる権利を持っています。
☆育つ権利
子どもたちは教育を受ける権利を持っています。また、休んだり遊んだりすること、様々な情報を得、自分の考えや信じることが守られることも、自分らしく成長するためにとても重要です。
☆参加する権利
子どもたちは、自分に関係のある事柄について自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、活動することができます。そのときには、家族や地域社会の一員としてルールを守って行動する義務があります。
開発教育に携わるとき、これらの権利はとても大きな意味を持ちます。世界には搾取や紛争・飢餓によって、健康に生きることのできない子どもたちがたくさんいます。その事実をしっかり受け止めることが必要だと思います。私たちは世界の現実を知らなければなりません。
子どもたちはみな‘生きる権利’を持っていると「子どもの権利条約」は謳っています。そしてその権利は、社会の一員としての義務を伴うというのです。54条からなるこの条約、条約ですから難しいです。でもなかなかおもしろいですよ
子どもの基本的人権を保障するために定められた条約です。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本が批准したのは1994年です。
「子どもの権利条約」には4つの柱となる権利があります。
「子どもの権利条約」-4つの柱
☆生きる権利
子どもたちは健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、健やかに成長する権利を持っています。
☆守られる権利
子どもたちは、あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られなければなりません。紛争下の子ども、障害をもつ子ども、少数民族の子どもなどは特別に守られる権利を持っています。
☆育つ権利
子どもたちは教育を受ける権利を持っています。また、休んだり遊んだりすること、様々な情報を得、自分の考えや信じることが守られることも、自分らしく成長するためにとても重要です。
☆参加する権利
子どもたちは、自分に関係のある事柄について自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、活動することができます。そのときには、家族や地域社会の一員としてルールを守って行動する義務があります。
開発教育に携わるとき、これらの権利はとても大きな意味を持ちます。世界には搾取や紛争・飢餓によって、健康に生きることのできない子どもたちがたくさんいます。その事実をしっかり受け止めることが必要だと思います。私たちは世界の現実を知らなければなりません。
子どもたちはみな‘生きる権利’を持っていると「子どもの権利条約」は謳っています。そしてその権利は、社会の一員としての義務を伴うというのです。54条からなるこの条約、条約ですから難しいです。でもなかなかおもしろいですよ