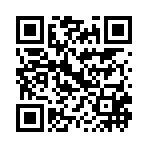2012年04月27日
開発教育を考える⑫
最近よく使われる言葉に「持続可能な~」という表現があります。英語のsustainable(サステイナブル)を日本語にした言い方です。sustainableという英語が国連の環境問題の分野で使われたことで広く世間で認知されるようになり、日本でも近年いろいろなところでこの表現が使われています。「持続可能な社会」「持続可能なエネルギー」「持続可能な開発」など…
開発教育の世界でも『持続可能な開発のための教育』(Education for Sustainable Development 通称ESD)という活動が行われています。ESDとはどんな活動なのでしょう?
ESDとは、社会の課題と身近な暮らしを結びつけ、新たな価値観や行動を生み出すことを目指す学習や活動です。
例えば、持続不可能な社会の課題を知り、その原因と向き合う。それらを解決するためにできることを考え、実際に行動する。そのような経験を通じて、社会の一員としての認識や行動力が育まれていきます。
また、豊かな自然といのちのつながりを感じたり、地域に根ざした伝統文化や人びとと触れながら、人と自然、人と人との共存や多様な生き方を学ぶといったことも、ESDのアプローチのひとつです。(認定NPO法人「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議(ESD-J)HPより引用)
国連や多くの国で取り入れられており、先日、ワクらぼ が参加した『世界中の子どもに教育を』というキャンペーンも世界規模で行われているESD活動の1つです。
市民やNGO・NPO、民間団体が地域で自主的に行っているものもたくさんあります。ワクらぼ の開催しているワークショップのいくつかは小さなESD活動だと考えています。
とはいえ、どんなことが、どんな方法が「持続可能」なことなのか? 逆に「持続不可能」とはどんな状態なのか? ちょっとわかりにくいですよね。言葉だけが流行りのように空回りしてしまうのも残念です。だから、いろんな手法にチャレンジしていこうと思います。
地球に住む、今を生きる私たちが、そして未来を作る子どもたちが、笑顔で健やかに、幸せに生きることのできる社会が「持続可能な」社会なのでしょう。難しい課題です。みんなでそのあるべき姿を考えていくことが大切なのだと思います
開発教育の世界でも『持続可能な開発のための教育』(Education for Sustainable Development 通称ESD)という活動が行われています。ESDとはどんな活動なのでしょう?
ESDとは、社会の課題と身近な暮らしを結びつけ、新たな価値観や行動を生み出すことを目指す学習や活動です。
例えば、持続不可能な社会の課題を知り、その原因と向き合う。それらを解決するためにできることを考え、実際に行動する。そのような経験を通じて、社会の一員としての認識や行動力が育まれていきます。
また、豊かな自然といのちのつながりを感じたり、地域に根ざした伝統文化や人びとと触れながら、人と自然、人と人との共存や多様な生き方を学ぶといったことも、ESDのアプローチのひとつです。(認定NPO法人「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議(ESD-J)HPより引用)
国連や多くの国で取り入れられており、先日、ワクらぼ が参加した『世界中の子どもに教育を』というキャンペーンも世界規模で行われているESD活動の1つです。
市民やNGO・NPO、民間団体が地域で自主的に行っているものもたくさんあります。ワクらぼ の開催しているワークショップのいくつかは小さなESD活動だと考えています。
とはいえ、どんなことが、どんな方法が「持続可能」なことなのか? 逆に「持続不可能」とはどんな状態なのか? ちょっとわかりにくいですよね。言葉だけが流行りのように空回りしてしまうのも残念です。だから、いろんな手法にチャレンジしていこうと思います。
地球に住む、今を生きる私たちが、そして未来を作る子どもたちが、笑顔で健やかに、幸せに生きることのできる社会が「持続可能な」社会なのでしょう。難しい課題です。みんなでそのあるべき姿を考えていくことが大切なのだと思います

Posted byワクらぼat19:33
Comments(0)
開発教育を考える