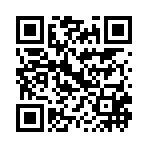2012年03月28日
水を考える
地球上には14億k㎥の水があるそうです。どのくらいの量なのか想像がつきませんが…
では、ここで問題です。この途方もない量の水のうち、海水はどのくらいを占めるのでしょうか?
答えは約97%。つまり、地球上の水のほとんどが塩分を含んでいるということになります。残り3%弱が淡水となりますが、その多くは北極、南極地域の氷だそうです。私たち人間が使うことのできる地下水、河川、湖沼にある淡水の量は、地球上の水の総量の僅か0.8%に過ぎません。そのほとんどが地下水なので、実際私たちが容易に手に入れることのできる川や湖の水はさらに少なくなって、総量の0.01%しかないそうです。0.01%の水でも人間の住むところに均一に供給されていれば、人間が生活するのに十分な量だというからそれもまたちょっと驚きです。本当に地球は「水の惑星」なのですね。
2012年3月6日に発表されたユニセフとWHO(世界保健機関)の合同報告書によると、国連のミレニアム開発目標(MDGs)の1つ、「安全な飲料水を利用できない人々の割合を半減する」という目標が、目標達成期限の2015年より早く達成されました。2010年末には世界の人口の89%が改善された水源を利用しています。2015年には92%になる見通しです。
しかし、世界では毎日3000人以上の子どもたちが下痢性疾患によって命を落としているという現実があります。不衛生な水を飲むことによりお腹を壊し、下痢による脱水症状で命を落とすのです。子どもを含め7億8000万人の人々がまだ安全な水を得られていないのです。残念ながら地球の豊かな水の恵みは、公平に私たちに与えられていません。
日本では蛇口をひねれば水が出ます。しかも水道水は日本中ほぼどこでもそのまま飲むことができます。水道水を飲んでおなかを壊すことはありません。
日本に暮らしていると忘れがちな水の大切さを、いろいろな数字から考えてみるのも大事なことではないでしょうか?
では、ここで問題です。この途方もない量の水のうち、海水はどのくらいを占めるのでしょうか?
答えは約97%。つまり、地球上の水のほとんどが塩分を含んでいるということになります。残り3%弱が淡水となりますが、その多くは北極、南極地域の氷だそうです。私たち人間が使うことのできる地下水、河川、湖沼にある淡水の量は、地球上の水の総量の僅か0.8%に過ぎません。そのほとんどが地下水なので、実際私たちが容易に手に入れることのできる川や湖の水はさらに少なくなって、総量の0.01%しかないそうです。0.01%の水でも人間の住むところに均一に供給されていれば、人間が生活するのに十分な量だというからそれもまたちょっと驚きです。本当に地球は「水の惑星」なのですね。
2012年3月6日に発表されたユニセフとWHO(世界保健機関)の合同報告書によると、国連のミレニアム開発目標(MDGs)の1つ、「安全な飲料水を利用できない人々の割合を半減する」という目標が、目標達成期限の2015年より早く達成されました。2010年末には世界の人口の89%が改善された水源を利用しています。2015年には92%になる見通しです。
しかし、世界では毎日3000人以上の子どもたちが下痢性疾患によって命を落としているという現実があります。不衛生な水を飲むことによりお腹を壊し、下痢による脱水症状で命を落とすのです。子どもを含め7億8000万人の人々がまだ安全な水を得られていないのです。残念ながら地球の豊かな水の恵みは、公平に私たちに与えられていません。
日本では蛇口をひねれば水が出ます。しかも水道水は日本中ほぼどこでもそのまま飲むことができます。水道水を飲んでおなかを壊すことはありません。
日本に暮らしていると忘れがちな水の大切さを、いろいろな数字から考えてみるのも大事なことではないでしょうか?

2012年03月26日
100人村ワークショップ
『世界がもし100人の村だったら』は、本のタイトルとしてご存知の方が多いと思います。もともとはアメリカの大学教授の、「世界を1つの村に例え、そこに暮らす人たちの人種や性別・世代、宗教や話されている言葉などの比率を簡単な数で理解してみよう」というアイディアがスタートだそうです。それがネット上で広まり、100人村となり、本となって紹介されました。
世界を100人の村に例えることで、世界の在り方(構成)が理解しやすくなっています。これを自分たちでも体感してみようというのが“ワークショップ版 世界がもし100人の村だったら”です。開発教育の世界では“貿易ゲーム”と並び有名なワークショップです。
開発教育というとちょっと堅苦しくて難しそう…と思われがちですが、参加してみるときっとイメージが変わりますよ。確かに開発教育のテーマは貧困だったり、紛争だったり、経済格差だったりしますが、その入り口は「世界を考える」「自国の外に眼を向けてみる」ということです。入口ですから、とっても間口が広いのです。国際交流や国際理解にもつながります。まずは入口だけでものぞいてみませんか?!
 4月21日(土) アイセル21 で『世界がもし100人の村だったら』のワークショップを開催します。あなたも100人村の村人の1人になって世界を体感してみてください
4月21日(土) アイセル21 で『世界がもし100人の村だったら』のワークショップを開催します。あなたも100人村の村人の1人になって世界を体感してみてください
世界を100人の村に例えることで、世界の在り方(構成)が理解しやすくなっています。これを自分たちでも体感してみようというのが“ワークショップ版 世界がもし100人の村だったら”です。開発教育の世界では“貿易ゲーム”と並び有名なワークショップです。
開発教育というとちょっと堅苦しくて難しそう…と思われがちですが、参加してみるときっとイメージが変わりますよ。確かに開発教育のテーマは貧困だったり、紛争だったり、経済格差だったりしますが、その入り口は「世界を考える」「自国の外に眼を向けてみる」ということです。入口ですから、とっても間口が広いのです。国際交流や国際理解にもつながります。まずは入口だけでものぞいてみませんか?!
 4月21日(土) アイセル21 で『世界がもし100人の村だったら』のワークショップを開催します。あなたも100人村の村人の1人になって世界を体感してみてください
4月21日(土) アイセル21 で『世界がもし100人の村だったら』のワークショップを開催します。あなたも100人村の村人の1人になって世界を体感してみてください
2012年03月23日
お出かけde国際理解①
青年海外協力隊で知られるJICA(国際協力機構)。静岡の窓口は名古屋にあるJICA中部です。そこにある『なごや地球ひろば』をご紹介します。
http://www.jica.go.jp/nagoya-hiroba/index.html
『なごや地球ひろば』は2009年に設立された、国際協力を様々なアングルから楽しんで体感できる施設です。開発途上国の現状や、直面している問題をパネル等で展示してあり、見学しながら学べます。入場料は無料です。青年海外協力隊で活動されていた方が「地球案内人」となって説明をしてくれます。国際協力や国際理解に関するさまざまなイベントも行われています。
 また、カフェクロスロードでは世界各国のメニューをお手頃価格で味わうことができます。
また、カフェクロスロードでは世界各国のメニューをお手頃価格で味わうことができます。
同じような施設が東京の広尾にもあります。こちらは『JICA地球ひろば』と言います。残念ながら広尾の施設は今年の8月一杯で閉鎖されてしまいますが、こちらのカフェ・フロンティアでもちょっと珍しいお料理が食べられますよ。ランチもあります。
近くにお出かけの時はぜひ足を運んで、国際協力を肌で感じてみてくださいね
http://www.jica.go.jp/nagoya-hiroba/index.html
『なごや地球ひろば』は2009年に設立された、国際協力を様々なアングルから楽しんで体感できる施設です。開発途上国の現状や、直面している問題をパネル等で展示してあり、見学しながら学べます。入場料は無料です。青年海外協力隊で活動されていた方が「地球案内人」となって説明をしてくれます。国際協力や国際理解に関するさまざまなイベントも行われています。
 また、カフェクロスロードでは世界各国のメニューをお手頃価格で味わうことができます。
また、カフェクロスロードでは世界各国のメニューをお手頃価格で味わうことができます。同じような施設が東京の広尾にもあります。こちらは『JICA地球ひろば』と言います。残念ながら広尾の施設は今年の8月一杯で閉鎖されてしまいますが、こちらのカフェ・フロンティアでもちょっと珍しいお料理が食べられますよ。ランチもあります。
近くにお出かけの時はぜひ足を運んで、国際協力を肌で感じてみてくださいね

2012年03月20日
開発教育を考える⑩
以前このテーマで外務省の『キッズ外務省』をご紹介しました。今回はユニセフのHPにある『子どもと先生の広場』をご紹介します。
http://www.unicef.or.jp/kodomo/index.html
ユニセフの組織や活動についての情報を中心に子どもたちにわかりやすく説明しているサイトですが、世界の子どもたちのデータをここから調べることができます。『世界子供白書』もここからダウンロードすることができますよ。開発教育の統計データを調べたい時に役に立ちます。
たとえば、『子どもと先生の広場』の中の、「世界の子どもデータ」に入って、「世界地図で見てみたい」から調べると、地図の上での子どもたちの格差がとてもよくわかります。アフリカでは、小学校に入学できても卒業まで通えない子どもの割合が60%以上の国がほとんどです。つまり10人中6人はせっかく入った小学校を卒業できないのです。そんな情報を私たちはインターネット上で簡単に見ることができるのですね。
なるべく多くの方に見て、知っていただきたいと思います。知るだけでは何にもならない、とおっしゃる方もいるでしょう。でも、‘知ること’は大事なことだと思いませんか?!‘知ること’は‘学ぶこと’であり、‘学ぶこと’は‘考えること’だと思います。そしてそこからいろいろなことが始まっていくのではないかと考えるのです。ぜひ一度のぞいてみてくださいね
http://www.unicef.or.jp/kodomo/index.html
ユニセフの組織や活動についての情報を中心に子どもたちにわかりやすく説明しているサイトですが、世界の子どもたちのデータをここから調べることができます。『世界子供白書』もここからダウンロードすることができますよ。開発教育の統計データを調べたい時に役に立ちます。
たとえば、『子どもと先生の広場』の中の、「世界の子どもデータ」に入って、「世界地図で見てみたい」から調べると、地図の上での子どもたちの格差がとてもよくわかります。アフリカでは、小学校に入学できても卒業まで通えない子どもの割合が60%以上の国がほとんどです。つまり10人中6人はせっかく入った小学校を卒業できないのです。そんな情報を私たちはインターネット上で簡単に見ることができるのですね。
なるべく多くの方に見て、知っていただきたいと思います。知るだけでは何にもならない、とおっしゃる方もいるでしょう。でも、‘知ること’は大事なことだと思いませんか?!‘知ること’は‘学ぶこと’であり、‘学ぶこと’は‘考えること’だと思います。そしてそこからいろいろなことが始まっていくのではないかと考えるのです。ぜひ一度のぞいてみてくださいね

2012年03月15日
参加者募集!ワークショップ開催

・・・「世界一大きな授業」キャンペーン参加・・・
『世界がもし100人の村だったら』
ワークショップ参加者募集!
日 時 : 平成24年4月21日(土)
13時30分~16時30分
場 所 : アイセル21(静岡市葵区東草深町3-18)
4階 第41集会室
参加費 : 500円
定 員 : 30人(申し込み順に受け付けます)
申込み : E-mail waku_labo@yahoo.co.jp または
Tel 090-2222-8639(担当:小山) まで
主 催 : ワークショップ らぼ・しずおか
毎年春、教育格差をなくし子どもたちが等しく学校に通えること願って、「世界中の子どもに教育を」という世界的なキャンペーンが展開されます。今年の開催は4月16日から30日まで。この時期、世界中のいろんな場所で、世界の教育の現状を学ぶ授業が行われます。これを「世界一大きな授業」と言います(ワクらぼ ブログ“開発教育を考える⑨”をご参照ください)。
日本でも小学生から社会人までいろいろな世代の人たちが、世界の子どもたちの現状を学びます。ワクらぼ ではこのキャンペーンに参加し、多くの皆様にキャンペーンのことをお伝えしたいと考えています。合わせて、今なお多い教育格差や貧困などの問題に眼を向け、世界の現状を一緒に考えてみようというイベントを実施します。今年は『世界がもし100人の村だったら』ワークショップです。ゲーム感覚で楽しみながら、ほんのちょっとだけですが世界の現状を体感できます。子どもから大人まで誰でも参加できます。
昨年の大震災では、世界中の多くの国や地域、団体や個人の皆様から温かい支援やご協力をいただきました。そんな今だからこそ、私たちも世界のことを考えてみませんか?
親子で、お友達同士で、仲間で、お誘い合わせてご参加ください!!

2012年03月14日
北街道の唄♪♪④
「森下よしひささんを偲ぶ会」が開かれることになりました。ワクらぼ では『北街道の唄』を何度かご紹介させていただきました。今回、有志の方が偲ぶ会を企画されるとうかがいご紹介させていただきます↓
http://www.kitakaidounouta-project.net/news.html
森下さんは鷹匠にあった『フォークテラス 海風』の店主であり、ご自身ライブ活動をされるミュージシャンでもありました。北街道をモチーフに『北街道の唄』という素敵な曲を作っています。残念ながら今年2月に病で亡くなられました。
森下さんは亡くなられましたが、『北街道の唄』は静岡の街唄として、森下さんの仲間に歌い継がれています。当日はその仲間たちのミニコンサートもあり、『北街道の唄』も歌われるとのこと。たくさんの方に聞いていただけたらと思います
http://www.kitakaidounouta-project.net/news.html
森下さんは鷹匠にあった『フォークテラス 海風』の店主であり、ご自身ライブ活動をされるミュージシャンでもありました。北街道をモチーフに『北街道の唄』という素敵な曲を作っています。残念ながら今年2月に病で亡くなられました。
森下さんは亡くなられましたが、『北街道の唄』は静岡の街唄として、森下さんの仲間に歌い継がれています。当日はその仲間たちのミニコンサートもあり、『北街道の唄』も歌われるとのこと。たくさんの方に聞いていただけたらと思います

2012年03月12日
開発教育を考える⑨
 国連のミレニアム開発目標(MDGs)は、
国連のミレニアム開発目標(MDGs)は、~2005年・・・初等・中等教育の男女格差解消
~2015年・・・初等教育の完全普及 という目標を掲げました。
確かに、学校に行けない子どもは少しずつ減っています。しかし、2010年現在も6,700万の子どもが学校に通っていません。2015年になっても5,600万人の子どもが学校に通えないことが予想されます。
学校に通えない子どものうち女の子の占める割合は50%を越えます。特にサハラ砂漠以南のアフリカでは1,200万人の女の子が1度も学校に通うことなく一生を終えます。
開発教育では、このような現実を一人でも多くの方に伝えることを目指しています。どうすれば伝わるのか?!工夫が必要になります。NGOやNPO、市民団体、教育機関やユニセフ、ユネスコなど様々な団体が、その特性を生かし広報、教育活動を実施しています。
広報活動の1つとして『世界中の子どもに教育を』という世界的なキャンペーンがあります。2003年に始まり、毎年4月に世界規模で行われます。
世界中の子どもたちが、「なぜ、世界には学校に行けない子どもたちがいるの?」「どうしたらみんなが学校に通えるようになるの?」「今、私たちにできることって?」といった教育に関する問題(開発教育)を、期間を定めて一斉に学びます。これを『世界一大きな授業』と呼んでいます。
日本では、途上国のこども支援を行うNGOからなる教育協力NGOネットワークがこのキャンペーンを実施しています。多くの教職員の方が参加され、小学校から大学までいろいろなところで授業が行われて生徒や学生が開発教育を学びます。昨年の参加校は270校、参加者は35,371名でした。(詳細はhttp://www.jnne.org/gce2012/をご覧ください。)
もちろん大人でも市民団体でもこのキャンペーンに参加できます。ワクらぼ も昨年からこのキャンペーンに参加しています。今年は、4月21日(土)アイセル21で『世界がもし100人の村だったら』のワークショップを開催します。(詳細は後日アップしますね!)
開発教育というちょっと堅苦しく難しそうな言葉が、広くたくさんの人々になじみ、気軽で参加しやすい活動になることを心から願っています

2012年03月11日
ワークショップ・雑記③
ゲームは気軽に楽しく参加できる体験型学習の1つです。ゲームという言葉から‘テレビゲーム’的なものを連想されがちですが、ワークショップのゲームはもっとアナログな感じです。どちらかといえばトランプや人生ゲームのようなイメージでしょうか。 カード(大きさはいろいろです。トランプやカルタを思い浮かべてください。)を使ったゲームもたくさんあります。昨年の12月に市政講座として ワクらぼ で企画させていただいたHUG(避難所運営ゲーム)ワークショップもカードゲームでした。そして、2月にメンバーの勉強会で体験した『お金の役割ゲーム』もカードゲームです。
カード(大きさはいろいろです。トランプやカルタを思い浮かべてください。)を使ったゲームもたくさんあります。昨年の12月に市政講座として ワクらぼ で企画させていただいたHUG(避難所運営ゲーム)ワークショップもカードゲームでした。そして、2月にメンバーの勉強会で体験した『お金の役割ゲーム』もカードゲームです。
防災・金融・貧困・教育・異文化理解・環境etc.様々な分野でカードゲームが作成されています。カードゲームは気軽に取り組める参加型学習です。ほとんどのカードゲームが、椅子と机があればどこでも開催できます。5~6人からできるゲームもあります。子どもはもちろん、大人でも(大人だからこそ)熱くなりますよ!日常なんかすっかり忘れてゲームに夢中になってしまうこともしばしば。あっという間に終了時間を迎えてしまいます。
おもしろくて、ちょっと勉強になるそんなゲームを一人でも多くの方に体験していただきたい!そう願っています。
24年度、 ワクらぼ ではいくつのゲームをご紹介することができるでしょう?!
 カード(大きさはいろいろです。トランプやカルタを思い浮かべてください。)を使ったゲームもたくさんあります。昨年の12月に市政講座として ワクらぼ で企画させていただいたHUG(避難所運営ゲーム)ワークショップもカードゲームでした。そして、2月にメンバーの勉強会で体験した『お金の役割ゲーム』もカードゲームです。
カード(大きさはいろいろです。トランプやカルタを思い浮かべてください。)を使ったゲームもたくさんあります。昨年の12月に市政講座として ワクらぼ で企画させていただいたHUG(避難所運営ゲーム)ワークショップもカードゲームでした。そして、2月にメンバーの勉強会で体験した『お金の役割ゲーム』もカードゲームです。防災・金融・貧困・教育・異文化理解・環境etc.様々な分野でカードゲームが作成されています。カードゲームは気軽に取り組める参加型学習です。ほとんどのカードゲームが、椅子と机があればどこでも開催できます。5~6人からできるゲームもあります。子どもはもちろん、大人でも(大人だからこそ)熱くなりますよ!日常なんかすっかり忘れてゲームに夢中になってしまうこともしばしば。あっという間に終了時間を迎えてしまいます。
おもしろくて、ちょっと勉強になるそんなゲームを一人でも多くの方に体験していただきたい!そう願っています。
24年度、 ワクらぼ ではいくつのゲームをご紹介することができるでしょう?!

2012年03月07日
味噌作り体験・記④
 2月11日に開催した『味噌作り体験 at 富厚里』。味噌作りを体験しよう、豚汁を味わいながら交流しよう、と参加者で楽しいひとときを過ごしました。
2月11日に開催した『味噌作り体験 at 富厚里』。味噌作りを体験しよう、豚汁を味わいながら交流しよう、と参加者で楽しいひとときを過ごしました。そんな今回の味噌作りには、もう1つ大きな取り組みがありました。
昨年起こった東日本大震災、あれから1年が経とうとしています。多くの犠牲が払われ、日本という豊かな国に大きな衝撃が走りました。国内・国外を問わず、たくさんの方々の支援の輪が広がり、被害を受けられた方々も日常を取り戻すためにがんばっていらっしゃいます。私たちも静岡から何かできないだろうか?と考えました。「せっかく味噌を作るのだから自分たちで作った味噌をわずかながらでも被災した福島の子どもたちに贈ろう!」との思いを参加者の皆さんにもご説明し、1人1.5kg分のお味噌を作りました。1.5kgうち0.5kgは福島の保育園や幼稚園の子どもたちに届けます。
福島ではいまだに放射線量の高い地区があるとのこと。様々な事情からそこで暮らさなければならない子どもやその保護者は、なるべく放射能の被害を受けないよう暮らしています。できるだけ汚染されていない食材を選んで調理したり、屋外に出ないようにしたり、かなりストレスのたまる生活を強いられているようです。お味噌のような、日々の暮らしで日本人にはなくてはならないものは、その調達自体が大変でしょう。そこで微力ながら、富厚里でとれた大豆を使い、自分たちで仕込んだお味噌を贈ることにしました。参加者30人、15kgのお味噌が作れました。さらにご指導いただいたさとう農園佐藤さん始め多くの方の善意が加わり、予定の倍以上のお味噌を6月末には福島に届けられることになりました。
 味噌作り当日も、福島の現状や子どもたちの様子を報告させていただきました。
味噌作り当日も、福島の現状や子どもたちの様子を報告させていただきました。ご協力いただきました皆様、本当にありがとうございました

今回の味噌作りにご協力をいただいた‘虹と緑しずおかフォーラム’やいくつかの団体・個人が実行委員会を作り、今月下旬には、飯館村の未就学児とその保護者の方を静岡に招いて、「はるやすみ 親子 わくわく ピクニック ~福島県 飯館から静岡へ 避難・保養プロジェクト~」が開催されることになっています。
2012年03月04日
開発教育を考える⑧
開発教育とは、世界で起こっている貧困・飢餓・紛争・環境破壊・人権侵害などの問題を取り上げ、その現状を知り、自分の置かれている立場で何ができるのかをみなで考え、行動を起こすきっかけとなる学びの場を作る活動です。
開発教育の統計的指標は国連から出される様々な白書をもとに提供されることがあります。
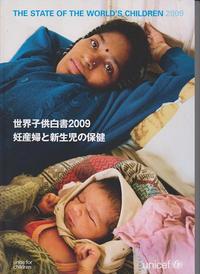 たとえば、世界各国の子どもたちがどんな状況にあるのかを知るにはユニセフ(国連児童基金)が1980年から刊行している『世界子供白書』が参考になります。この白書には世界の貧困国や途上国の子ども、幼児の栄養や教育の状態が数字で統計的にまとめられています。また毎年テーマを決めて、そのテーマに関する詳細な現状分析や活動方針などを論じています。2011年のテーマは『青少年期<10代>可能性に満ちた世代(Adolescence An Age Of Opportunity)』でした。読み応えのある白書に仕上がっています。
たとえば、世界各国の子どもたちがどんな状況にあるのかを知るにはユニセフ(国連児童基金)が1980年から刊行している『世界子供白書』が参考になります。この白書には世界の貧困国や途上国の子ども、幼児の栄養や教育の状態が数字で統計的にまとめられています。また毎年テーマを決めて、そのテーマに関する詳細な現状分析や活動方針などを論じています。2011年のテーマは『青少年期<10代>可能性に満ちた世代(Adolescence An Age Of Opportunity)』でした。読み応えのある白書に仕上がっています。
白書に収められた数字がすべて確実なものかどうかの判断は難しいところです。なぜなら、貧困国の中には国が国家として機能せず、統計を取ることさえ困難なところもあるからです。また多くの国には数字だけではとらえきれない様々な問題が隠されています。ただ、開発教育を学ぶとき、具体的な数字を示されることでその問題がぐっと身近に感じられることも事実です。その意味で、国連をはじめ国や実績のあるNGOなどが発表している資料を活用することはとても大切なことだと考えます。
ワクらぼでは、出来るだけ具体的にわかりやすく、そしてなるべく正確な情報を提供し、世界の現状をお伝えしていけるように努力していきたいと考えております
開発教育の統計的指標は国連から出される様々な白書をもとに提供されることがあります。
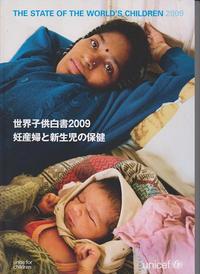 たとえば、世界各国の子どもたちがどんな状況にあるのかを知るにはユニセフ(国連児童基金)が1980年から刊行している『世界子供白書』が参考になります。この白書には世界の貧困国や途上国の子ども、幼児の栄養や教育の状態が数字で統計的にまとめられています。また毎年テーマを決めて、そのテーマに関する詳細な現状分析や活動方針などを論じています。2011年のテーマは『青少年期<10代>可能性に満ちた世代(Adolescence An Age Of Opportunity)』でした。読み応えのある白書に仕上がっています。
たとえば、世界各国の子どもたちがどんな状況にあるのかを知るにはユニセフ(国連児童基金)が1980年から刊行している『世界子供白書』が参考になります。この白書には世界の貧困国や途上国の子ども、幼児の栄養や教育の状態が数字で統計的にまとめられています。また毎年テーマを決めて、そのテーマに関する詳細な現状分析や活動方針などを論じています。2011年のテーマは『青少年期<10代>可能性に満ちた世代(Adolescence An Age Of Opportunity)』でした。読み応えのある白書に仕上がっています。白書に収められた数字がすべて確実なものかどうかの判断は難しいところです。なぜなら、貧困国の中には国が国家として機能せず、統計を取ることさえ困難なところもあるからです。また多くの国には数字だけではとらえきれない様々な問題が隠されています。ただ、開発教育を学ぶとき、具体的な数字を示されることでその問題がぐっと身近に感じられることも事実です。その意味で、国連をはじめ国や実績のあるNGOなどが発表している資料を活用することはとても大切なことだと考えます。
ワクらぼでは、出来るだけ具体的にわかりやすく、そしてなるべく正確な情報を提供し、世界の現状をお伝えしていけるように努力していきたいと考えております