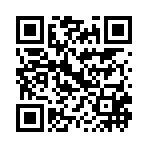2012年01月18日
開発教育を考える①
‘開発教育’は英語の Development Education を日本語に訳した言葉です。1960年代、開発途上国でボランティアをしていた人たちによって始められた教育です。「経済的に豊かな先進国が地球上の北に多く、経済的に貧しい開発途上国が南に多い」という南北問題が盛んに議論されていたころ、その格差を少しでもなくし、誰もが豊かな社会に生きるためにはどうしたら良いのか、という思いから‘開発教育’は生まれました。開発途上国の支援から生まれた活動です。
現在も開発途上国の現状を伝えたり、その支援を考えたりする教育として活用されています。それに加え、現代社会に生まれた様々な問題も取り上げられるようになってきました。貧困・格差・環境破壊などの問題は、外的(国際的な)問題だけでなく、内的(国内的な)問題として社会に存在します。それを様々な角度から取り上げ、考えていくのが‘開発教育’の今の在り方です。
‘開発教育’は何よりも市民自らが参加し考えることを大切にしています。人としての尊厳をお互いが認めあえる公正な社会づくりをめざして、いかに生きるべきかを考える場を多くの人達に提供するための教育活動です。
ワクらぼ ではワークショップを通してこの‘開発教育’に取り組んでいきます
現在も開発途上国の現状を伝えたり、その支援を考えたりする教育として活用されています。それに加え、現代社会に生まれた様々な問題も取り上げられるようになってきました。貧困・格差・環境破壊などの問題は、外的(国際的な)問題だけでなく、内的(国内的な)問題として社会に存在します。それを様々な角度から取り上げ、考えていくのが‘開発教育’の今の在り方です。
‘開発教育’は何よりも市民自らが参加し考えることを大切にしています。人としての尊厳をお互いが認めあえる公正な社会づくりをめざして、いかに生きるべきかを考える場を多くの人達に提供するための教育活動です。
ワクらぼ ではワークショップを通してこの‘開発教育’に取り組んでいきます